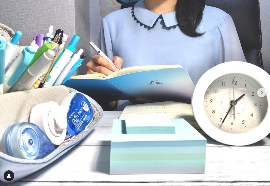時間〈とき〉ラボ運営事務局 さん

「わたしの時間〈とき〉デザイン」では、時間〈とき〉をデザインしている方の取り組みや考え方、ライフスタイルのMyルールなどをご紹介していきます。
今回は、美術館や博物館、駅、庁舎など、数多くの建築を手がけてきた建築家・内藤廣さんにお話を伺いました。
多忙をきわめる日々の中で、40年にわたり向き合い続けてきたのが能率手帳。覚えておきたいこと、心に残った風景を、時に貼り込み、時に描き込む。その手帳時間は、内藤さんにとってどんな意味を持っているのでしょうか。

※記事で使用している展示写真は、許可を得て撮影しています。一般の来場者による手帳展示の撮影はできませんので、ご注意ください。
現在、東京都千代田区・紀尾井清堂で開催中の「建築家・内藤廣 なんでも手帳と思考のスケッチ in 紀尾井清堂」を訪ね、展示されている40年分の手帳の思い出とともに、手帳や時間について語っていただきました。

■内藤廣 【建築家・東京大学名誉教授】
1950年生まれ。1976年早稲田大学大学院修士課程修了後、フェルナンド・イゲーラス建築設計事務所(スペイン・マドリッド)、菊竹清訓建築設計事務所を経て、1981年に内藤廣建築設計事務所を設立。2001〜11年東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻にて教授、同大学にて副学長を歴任。2011年〜同大学名誉教授。2023年4月から多摩美術大学学長。
主な建築作品に、海の博物館、牧野富太郎記念館、倫理研究所富士高原研修所、島根県芸術文化センター、静岡県草薙総合運動場体育館、富山県美術館、とらや赤坂店、高田松原津波復興祈念公園 国営 追悼・祈念施設、東京メトロ銀座線渋谷駅、京都鳩居堂、紀尾井清堂など。
近著に『内藤廣と若者たち 人生をめぐる一八の対話』(鹿島出版会)、『内藤廣の頭と手』(彰国社)、『内藤廣設計図集』(オーム社)、『空間のちから』(王国社)、『建築の難問 〜新しい凡庸さのために』(みすず書房)、『建築家・内藤廣 Built と Unbuilt 赤鬼と青鬼の果てしなき戦い』(グラフィック社)、『建築家・内藤廣 赤鬼と青鬼の場外乱闘』(グラフィック社)などがある。
● 切る・貼る・書く。40年間の手帳使いを振り返る
− 今回この紀尾井清堂に約40年分の手帳がずらりと並んで、改めてどんなお気持ちですか?
内藤:いやあ、よくここまでやってきたなあ・・・という気持ちです。自分のやっていることが40年の間に変わってきたようで案外変わらないんだな、とも思いましたね。
− 40年前、能率手帳を使い始めたのはどんなきっかけからだったのですか?
内藤:実は大したきっかけはなくて、標準タイプの手帳を探して、たまたま手に取ったのが能率手帳でした。もちろん世の中にまだインターネットなんて普及していない時代。手帳で予定管理するのに、小さい手帳ではぐちゃぐちゃになってしまうので、このA5サイズの能率手帳を使ってみようかと。そんな偶然から始まりました。最初の数年はいろんな手帳を試して、最終的に落ち着いたのがA5サイズの能率手帳です。

※許可を得て撮影
− 手帳に書き込むだけでなく、いろんなものを貼り込むようになったのはなぜだったのですか?
内藤:仕事の際に事務所の所員が描いた図面に僕がスケッチを入れていく作業を何度も繰り返すのですが、途中段階の図面はいわば消耗品のようなもので、どんどん捨てていってしまうから手元に残らないんです。でも、その過程の中で自分の記憶を反芻するというか、途中の図面とスケッチをときどきは残しておいて、立ち戻って考えることをしてみたらどうかなと考えて、途中段階のスケッチを手帳に貼ってみたのが始まりです。

仕事の図面だけでなく、その時期に観に行って印象的だった展覧会とか演劇とか、そういうものも覚えておきたいと思って、チケットだったりチラシだったり、いろんなものを貼るようになっていきました。手帳は人に見せる前提にはしていないので、個人的にその時に大切なものを貼り込んでいます。僕にとって能率手帳はベーシックなキャンバスという感じです。

※許可を得て撮影
− 貼り込みもあれば、サラサラっと手帳のページに描き込まれたスケッチなどもあり、拝見していて興味深かったです。
内藤:「この風景を覚えておこう」と思うと、僕はスケッチをするんです。その場で直接手帳に描き込むこともあるし、ちょうど近くに置いてある紙、例えばレストランの紙ナプキンなどに描いて後で貼り込むこともあります。あとは、ちょっと特殊能力なのかもしれないけれど、その時見た風景を覚えておいて、例えば旅先なら宿に戻ってから夜に手帳に描き込むこともよくやりますね。覚えておきたい風景は、写真を撮るのではむしろ覚えられない。目で見ることで覚えます。写真はパッと撮って安心してしまうところがありますが、頭で覚えようとすると、細かいところまでよく見るようになりますから。事務所の所員にも、写真に撮らずに、目で覚えることをしなくてはダメだよと、よく言っています。

※許可を得て撮影
− それは驚きです。思い出して後で描いたとは思えないほど、その場の空気感が繊細に伝わるすてきなスケッチだと感じました。
内藤:この「見て覚えて描く」という原点は、50年近く前、まだ20代だった時にシルクロードを旅した経験にあります。当時、シルクロードの旅では写真を撮影してはいけない場所がたくさんあって、見たものを覚えておきたいと思ったら、頭に焼き付けておいて、後で描くしかなかったんです。それから、バスで移動するでしょう。そうすると景色がどんどん変わっていって、それも覚えておきたいと思って一生懸命見ていましたね。
そんなことから風景を頭で覚えるようになったわけですが、これがとてもいいのが、どんなに時間が経ってもその時の景色を呼び出せること。今でもそのシルクロードの旅で見た、例えばアフガニスタンのカンダハール、向こうの方にお城が見えて手前にイスラームの墓地があって・・・という風景を、今ここで描いてと言われれば描けるわけです。そんなふうに記憶の引き出しに入っている数々の風景が、スケッチとして手帳に貼り込まれています。

※許可を得て撮影
− 展示を拝見すると、たくさんの記憶が貼り込まれ、そして描かれた内藤さんの能率手帳は、どの年もとても分厚く仕上がっているのが印象的です。
内藤:1年間使い終えると、だいたい元の3倍くらいの厚さになっているんじゃないかな。毎年1年の終わり頃に、少しだけ手帳を整理して、分厚い1冊ができあがると「1年終わりました」という感じになり、それで次の年に向かっていく。この流れが僕にとって1年を終える際の恒例になっていますね。
 ※許可を得て撮影
※許可を得て撮影
● 建築にも手帳にも通じる「時間を味方につける」という価値観
− 能率手帳の考え方は時代とともに変化し、かつての「時間を管理する」という役割にとどまらず、「時間〈とき〉デザイン」をコンセプトに、未来を創るために「時間をデザインする」手帳としての価値観も発信しています。この “時間“ というものを内藤さんはどのように捉えていますか?
内藤:時間・・・僕の仕事においてはほとんどそのことばかり考えていると言ってもいいかもしれない。そのくらい大切なことです。というのは、建築というのは50年あるいは100年と時代を超えていくものだと思っていて。だからこそ時間を味方につけていかなければならない。そうしなければ瞬く間に社会に消費されて、見捨てられていく運命にある。いかに時間を味方につけるか、建築の小さな部分から全体までそれに尽きる。それこそが建築であるべきだと思っています。
社会は情報化して、デジタル化して、どんどん細切れになっていますよね。そんな中でも、建築だけはその反対側にいなければならない気がしています。それは人間も同じで、時間を味方につけていかないとどんどん薄っぺらになってしまうのではないでしょうか。

− 時間を味方につける。それは手帳にも共通する価値観と言えるかもしれません。
内藤:おそらく手帳も、経済が急成長していく時代に、効率よくやるためにどうやって時間を管理していくかという意味合いで浸透していったものですよね。その意味づけも、今はまったく違ってくるのではないでしょうか。それこそスマホもパソコンも普及している現代は、効率のよさだけを求めたら時間管理もそういったツールでやればいいわけで、ひょっとしたらAIがタイムスケジュールを全部組んでくれるようになるかもしれない。
そんな中で手帳というものは、時間を管理するためという以上に「自分を取り戻すため」という意味を持つようになってきているのではないでしょうか。自分で考えて、自分を取り戻すための時間。そのための媒体が手帳になっているように思います。
− 内藤さんにとっては、手帳と向き合う時間はどんな意味を持っていると感じますか?
内藤:手帳に向き合う時間は、僕にとってはとても神聖な時間ですね。建築家の仕事というのは雑用の山で、日々たくさんの人に会い、たくさんの事柄に対処しなければなりません。そうすると疲れてきて、自分がよくわからないという状態になる時もある。だけど、そんな時に手帳にいろいろと切り貼りしたり、描いたりしていると、頭が整理される感じがするんです。

− それが、例えばパソコンやスマホで日記を書くといったこととは少し違ってくるのはなぜだと思いますか?
内藤:切り貼りしている時はきっと無心の状態なんでしょうね。頭で考えるというよりも、手で考えている感覚。だから無心になれるのだと思います。手で考えていると、自分というものがよくわからなくなっていたところから、ふっと我に返る。だから本当に、自分を取り戻す時間なんです。
おそらく効率化だけを目的に能率手帳を使っていたら、こんなに長く続かなかったでしょう。もし手帳がなかなか続かないという人がいるとしたら、自分を取り戻す時間、そのための大切なツールだと捉えて向き合ってみるとまた違ってくるように思います。

※許可を得て撮影
− 過去の手帳を開き、振り返ることもありますか?
内藤:そうですね、何かきっかけがあったりすると、ときどき見返して振り返ることもあります。基本的に人間というものは忘れやすいし、忘れるからこそ生きていけるのかもしれない。でも、ときどき思い出す必要がある場面もあって、それが可能なのも手帳だからこそかなと思います。

どの年の手帳も振り返ってみればそれぞれに忘れがたい1冊になっていて、「こんな年だったか」と思う1年もあれば、「辛かったな」という1年もあります。東日本大震災の復興に関わり始めた2011年以降の手帳は振り返ると、うん・・・やはり辛かった。
被災地のリアルな声に向き合うことと、建築家としてやらなければならない仕事との間にいた時期です。そんなことを考えてみると、手帳はすごいなと思います。だって、開けばその時の感覚がありありとよみがえってきますから。

※許可を得て撮影
− その時々の思いや感覚が込められた40冊の手帳。最後に、改めて今回の展覧会の見どころを教えていただければと思います。
内藤:もちろんいちばん見ていただきたいのは40年分の手帳ですが、でも、この紀尾井清堂の空間もぜひ楽しんでほしいです。ここの空間は、僕がこれまでやってきたこと、造ってきた建築にかなりシンクロしていると思いますので。手帳と空間、その両方を楽しんでいただけるとうれしいです。

● 編集後記
約40年分の手帳に込められた記憶や思考をたどりながら、内藤さんの「時間〈とき〉」との向き合い方を感じ取ることができる取材でした。建築という長い時間軸を生きる仕事を通して培われた、「時間を味方につける」という言葉がとても印象的で、その視点は、日々の手帳の使い方や時間の捉え方にも深く通じるものだと感じます。
手で考える。風景を目で覚える。忘れることと、思い出すことのあいだにある、静かで豊かな時間。効率では測れない時間の価値を、内藤さんの言葉や手帳からあらためて教わったように思います。
展示会では、厚みを増した一冊一冊の手帳に宿る時間の形とともに、内藤さんの見た景色や思考のスケッチにも触れることができます。ぜひご自身の時間〈とき〉についても考えていただける機会になればうれしいです。
● 展覧会概要
建築家・内藤廣 なんでも手帳と思考のスケッチ in 紀尾井清堂
内藤さんが設計を手がけた紀尾井清堂を会場に、約40年間使い続けている能率手帳の現物を年代別に展示した同展。手帳に貼り込まれたアイデアの断片、チケットの半券、描き込まれたスケッチなどを間近に見ながら、その時々の思考や思い、時代の空気感などを感じることができます。
会期:2025年7月1日(火)〜9月30日(火)
開館日:火・木・土曜日(祝日・年末年始等を除く)
※令和7年8月12日、8月14日、8月16日、9月23日は閉館となります。
開館時間:10:00〜16:00(最終入館 15:30)
入場料:無料(予約不要)
会場:倫理研究所 紀尾井清堂(東京都千代田区紀尾井町3-1)
アクセス:JR四ツ谷駅/地下鉄麹町駅・赤坂見附駅・永田町駅 各駅より徒歩圏内