時間〈とき〉ラボ運営事務局 さん

町田そのこ(まちだ そのこ)
福岡県在住。2016年「カメルーンの青い魚」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞。選考委員の三浦しをん氏、辻村深月氏から絶賛を受ける。翌年、同作を含むデビュー作『夜空に泳ぐチョコレートグラミー』(新潮社)を刊行。他著書に『ぎょらん』『うつくしが丘の不幸の家』(東京創元社)などがある。『52ヘルツのクジラたち』(中央公論新社)で2021年本屋大賞受賞。
聞き手:日本能率協会マネジメントセンター 代表取締役 張士洛
まずは重版がかかることが目標。
4作目で、みごと本屋大賞を受賞

張:『52ヘルツのクジラたち』が、2021年の本屋大賞を受賞されました。まずは、率直に受賞のご感想をお聞かせいただけますか。
町田:私は福岡県に住んでいるのですが、地元にいると、東京の様子がわからず、「本当だろうか?」と思っていました。でも、こうして喜んでくださっている皆さんの姿を見て、「本当だったんだ!」と実感した次第です。
『52ヘルツのクジラたち』が出たのは、1年前、コロナ禍で最初の緊急事態宣言が出た頃だったので、まだまだ駆け出しの自分が、こんな大変な中で出版しても大丈夫だろうか。埋もれてしまうのではないかと思っていたんです。それが結果として1年後に、賞をいただいてこうしてお話しをしている。本当に信じられない気持ちでいっぱいです。
張:まさに夢に手が届いたという。これまで作家としてはどんな目標を設定されていらっしゃったのですか。
町田:『52ヘルツのクジラたち』は4作目ですが、一度も重版がかかったことがなかったので、目標としては重版を1回かけることでした。
張:実に謙虚な目標ですね(笑)。
町田:「重版かかりました」という連絡を受けて、「もう思い残すことありません」って言ったくらい。これまでは、書店さんに自分の本が平積みにされることなんてもちろんないし、地元の大きな書店さんでも棚挿しで1冊あればいいといった程度。それが、平積みにしていただいたり、コーナーをつくってくださっていたりと、本当に夢を見ているみたいです。
でも、自分の本をここまで大きなものに育ててくださったのは、自分の手柄ではなく、営業の方をはじめ、いろいろな方が裏で頑張ってくださったんだと思っています。
張:じっくり読ませていただきましたが、深いですよね。よくこういうタイトルをつけたなと思いました。52ヘルツのクジラは、海洋生物のことを調べていて知ったそうですが、なぜ海洋生物を調べてらっしゃったのですか。
町田:デビュー作が熱帯魚を扱う短編だったのですが、そこから、海洋生物を主体にした短編連作集にしたいというお話になって、変わった海洋生物を調べていたんです。
例えば、ウツボは、成長とともに体色がブルーから黄色に変わるのですが、その時にオスからメスに変わるものがいるんです。そういう面白い、物語に落とし込めるネタはないかと調べていたときに、52ヘルツのクジラのことを知りました。ただ、52ヘルツを題材にした話は、そのとき書いていた短編には納めきれないだろうと思って、いずれ自分が実力をつけて長編にチャレンジするときまでとっておこうと思ったのです。それで数年間、アイデアを寝かせていたのです。
自身の出産を機に、
児童虐待への関心が芽生える

張:作中に愛(いとし)という声を出せない、しかも虐待を受けている少年が出てきます。そういう少年を登場人物にした理由は何でしょうか。
町田:私は出産を経験して、いまも子育て中ですが、それまでは正直なところ、虐待問題に関してはさほど関心がありませんでした。でも自分が子どもを産んで、子どもの世話に必死になっている一方で、虐待するってどういう心理なんだろうと、すごく気にするようになりました。
そういうなかで虐待のニュースに接したときに、どうやったら助けられるんだろう、また周りはどうしたら気づいてくれるんだろう。そういうことを漠然と考えるようになったのです。そんなタイミングで長編のお話をいただき、52ヘルツをやっと使えるなと思いました。虐待の問題をここで自分なりに一度検証して、自分ならどうやって助けるだろうかという答えを導き出したいと思って、書き始めました。
張:難しい問題なので、答えは一つではない。でも、作品をきっかけに、なんとかしたいと思う人が一人でも増えてほしいというメッセージですね。
町田:そうだといいですね。作品を読んだ人のなかには、それが正しい助け方ではないと思う人もいるでしょう。でも、それはそれで正しい読み方だと思います。そういうふうに、たくさんの人が読んで、話してくれたら嬉しいと思います。
小学生のときに出会った
氷室冴子さんの作品に救われる
張:さて、町田さんご自身のことについても伺いたいのですが、お母様が大変読書好きで、お母様と本を取り合うようにして読んでいたとのことですが。
町田:小学校3年生の時に、氷室冴子さんの小説と出会いました。それまでは、絵本とか漫画ばかり読んでいて、小説に触れたのは氷室さんの作品が生まれて初めてでした。すごく面白くて、そこから夢中になったんです。母も氷室さんが好きで、2人で読んで感想を語り合いました。そこから、「私もこういうのが書けたらいいな」と思うようになっていきました。
張:具体的にどんな感想を持たれたのですか。
町田:実は、小学校の5年生から6年生の頃、いじめに遭っていました。そのことを母にも学校の先生にも言えなかったのです。そういうなかで、休み時間に独りで氷室さんを読んでいたのですが、氷室さんの作品に出てくる女の子たちはみんな芯があって強いので、自分で困難を乗り越えていく登場人物たちに応援されているような気持ちになりました。毎日辛くても、氷室さんの新刊が出ると思うと、明日の生きる活力になった。氷室さんの作品に、背中を押してもらっていたのです。
そういう日々の中で、必ず小説家になって氷室冴子さんに会って、「あなたをめざして作家になった」「あなたのおかげでなれたんです」と、本人を前にして言うんだ、という夢を抱くようになりました。作家になりたいというよりも、作家として氷室冴子さんに会いたいというのがすべてでした。
張:いじめに遭っていたことを、2年間もお母様にも言えないとは、お辛かったでしょうね。
町田:ずっと辛い思いをしているなか、あるとき、作文だったら先生にどれだけ自分が辛い思いをしているのかを、客観的に知ってもらえるんじゃないかと考えて、ノートに先生に宛てた手紙を書きました。でも出す勇気がなかったんですね。そうしたら母親が、何を一生懸命書いてるのかと思ったらしく、机にしまっていたノートを発見したのです。それで驚いて、そのままノートを持って先生のところに行ってくれて、問題が解決していきました。そういう意味でも、私は文章に救われているのかもしれません。
張:お母様の話が出ましたが、作中それぞれの登場人物の母との関係もたくさん描かれていると思いました。主人公の貴瑚のお母さんも、愛のお母さんも、そしてアンさんのお母さんもそうですし。
町田:私の母親は良妻賢母タイプというか、夫を立てて子どもたちの面倒をよく見て、そして自分のことは二の次っていう人でした。だから私も結婚して子どもを産めば、自動的にああなるんだろうと漠然と思っていました。ところが、子どもを産んでも一向にそうならなくて(笑)。周りの友達を見ても昔のまんま母親になっている。娘と自分の関係性と、私と母の関係性も全く違う。不思議なものだなと。そこから、どうやったら母親になれるんだろうか、母親像って何だろうか、母親との付き合い方って何だろうかって思い始めたのです。なので、これからは物語の中で、母と子のあり方をいろんな角度で書いてみたいと思っています。次のテーマですね。
ケータイ小説で出会った仲間たちに
背中を押してもらう

張:氷室さんをめざして作家になりたいと願った。しかし、現実はOLとして働くことになるんですよね。一度離れてしまった作家への夢を、どうやって現実のものにしていったのですか。
町田:結婚、出産をへて、専業主婦になったときに、何者にもなれていない自分に気づきました。子育てや家庭はもちろん大事ですが、現状になんとなく満足できなかったのでしょう。そんなときに、氷室さんが亡くなられたことを知ったんです。それを新聞の訃報欄で見つけたときに、「私はこの人に会いたくて作家になりたかったのに、何やっているんだ。もっと頑張って書いていたら、どこかで会えたかもしれないのに、もう二度と会えないじゃん」と、自分のことがすごく嫌になってしまったのです。そういう気持ちが「書く」という行動につながっていきました。氷室さんにはもう会えないけれど、せめて作家になる夢は追いかけようと。
張:そういう意味では、二度、助けていただいたんですね。
町田:そうです。氷室さんは私の人生の要所において、背中を押してくれたんですね。でも、もっと早くから頑張っていれば、もしかしたらどこかでお会いできたんじゃないかって、それは今でも悔やんでいます。
張:氷室さんが亡くなられて、また書こうと決心するまでは、どんな活動をしていたのでしょうか。
町田:心の隅でなんとなく「小説家になりたい」という夢はありましたが、生活に追われていました。読むには読んでいたので、夢だけで満足していたのかもしれません。
張:そんななかで、書くほうはどうやって上達させたのですか。
町田:高校生までは趣味で書いていました。演劇部の友達に頼まれて台本を書いたこともありましたが、高校を卒業した後、なぜか畑違いの理容学校に進みました。でも不器用だったので、モノにはなりませんでしたが(笑)。結婚後は生活が忙しくて、本を読むのも疎かになっていたのですが、書くリハビリをしなければと、当時流行っていた、ケータイ小説に投稿するようになりました。ケータイ小説は、乳飲み子を抱えていても携帯一つあれば書けます。そこで何年か修行みたいに投稿を続けました。人気はイマイチでしたが、リアルの読者さんたちから、面白かったとか、この展開は都合がよすぎるとか、意見がもらえるところが魅力でした。漢字が多すぎるとか、行が詰まって読みにくいとか、そういう指摘もありました。今思うと、すごくいい勉強になりましたね。
張:直接、読者とつながっていて、反応も早いと。
町田:「いいね」ボタンもあったし、読者の数もわかるので、モチベーションになりました。私は売れなかったのですが、周りの投稿仲間には才能がある人もいて、そういう人の作品は、どんどん書籍化されていくんです。それを、指をくわえて見ていたのですが、そういう投稿仲間に「一度、出版社に送ってみたら」って提案してくれた人がいました。でも、出版社に原稿を送るのは、当時の私にとって、とても敷居が高い。けっこう迷ったのですが、「大丈夫だよ」と背中を押してくれたのです。そこで、新潮社さんの「女による女のためのR-18文学賞」に応募しました。この賞は、原稿用紙30枚から50枚という短編だし、WEBで送稿できたので、ケータイ小説の延長みたいな感覚で応募できたのです。
張:それが、現在へと続く足掛かりになったのですね。
町田:最初に応募したときは一次選考にも引っかかりませんでした。全然レベルが足りていないんだと思って、そこから約2年間、自分なりに独学で作家になる勉強をしました。そして、再度チャレンジして送った作品で大賞をいただくことができ、デビューとなったのです。ですから、私の作家としての転機は、いじめに遭っていた時代に読んだ氷室さんの作品と、氷室さんが亡くなって「書かなくては」と思ったとき、そしてR-18文学賞への応募という3つだったと思います。
3つめの、応募を後押ししてくれたケータイ小説のお友達は、私よりも随分早く作家になっていますが、ずっと「あなたは面白いものが書けるから大丈夫だよ」って応援を続けてくれました。そういう同じ立場にいて応援してくれる友達がいまも4、5人いるのですが、彼女たちとの出会いもすごく大きいですね。作家ってけっこう孤独なものだと思うんですよ。そういうときに同じ夢を追っている人たちと出会って、仲良くなれたことは、とても貴重だったと思います。
「空っぽ」になったときは、
美術館でインスピレーションを得る

張:作家として創作活動を行う、町田さんのクリエイティビティの源泉はどこにあるのでしょうか。
町田:自分の中で、「空っぽになったな」って思ったら、普段手に取らないものを手に取ったり、行かない場所に行ったりします。私は体を動かすことが苦手で、しかも出不精なので、普段はあまり外に出ないのですが、それでも無理に足を伸ばして生活圏から少し離れたところに行くと、刺激が得られることがあります。
たとえば、徳島県の大塚国際美術館に行くと、インプットというか、何か大きなものを得られる気がします。膨大な美術品を前に、足を棒にして歩き回った後は、すごく豊かになった気になるんです。こうやって自分に足りないものを補充していくんだと。
張:世界の名作をオリジナルと同じ大きさで複製して展示している、素晴らしい美術館ですよね。
町田:そうなんですよ。原寸大のゲルニカに触れることもできますし、とにかくすごい。芸術にどっぷり浸ることができるんです。そのあとで本物を見にいくと、またそこで本物のパワーを感じることができます。
張:創造という観点でもう一つ。今回の作品の登場人物の設定は、どのようにして思いついたのですか。
町田:自分の身近にいる人をモデルにすることが多いですね。また、私は転職を何度か経験しているので、それぞれの職場で出会ったちょっと面白い人からもヒントを得ています。あの人なら、きっとこんなことを言うだろうなと想像して、その言葉を掘り下げながら、バックボーンを設定していくのです。
張:主人公の貴瑚は、どんなイメージで設定されたのでしょうか。
町田:見た感じは特におかしなところはない、ごく普通の女の子だけど、ちょっとしたほころびがある。なぜなら、それは虐待を受けていたから、という感じでしょうか。たとえば、愛くんを「52」という変わった名前で呼んでいたのも、貴瑚自身が虐待を受けていたから、なぜ変わっているのかが分からない。52は、貴瑚にとっては意味があるし、愛情を込めて呼んでいる。だからおかしくないと感じている。そういうちょっとしたほころびですね。
張:ほかにも個性的なキャラクターが登場しますが、とくに思い入れのあるキャラクターは誰でしょう。
町田:田舎のおばあちゃん軍団ですかね。田舎で生まれ育った自分も、同じような人たちに囲まれて生きてきましたから。車に派手な装飾をすると文句を言われたり、髪の毛を染めると不良だと言われたり、車の助手席に男の人を乗せていると、「知らん男のせとったばい」と言われたり(笑)。そういうリアリティは出せたんじゃないかなと。
自分が成長できるのが豊かな時間。
豊かになっておすそ分けしたい

張:さて、続いては町田さんにとっての「時間デザイン」についても伺いたいと思います。ご自身にとって「豊かな時間」「時間をデザインしている」という感覚が得られるのは、どんなときでしょうか。
町田:「豊かになる」ということは、自分自身を満たすことだと思っています。足りていないと、周囲にとっても良くないと思うんですよ。いつも何かに追われてピリピリしているお母さんだったら、子どもたちも卑屈になってしまう。そうでなく、いつも豊かであれば、周りも豊かにできるし、それをみんなにお裾分けできます。
そして、豊かな時間とは、自分の成長が実感できる時間です。たとえば、美術館で過ごす時間とか、本を読んでいる時間とか、そういう時間って、確実に自分を成長させてくれると思うんです。
張:1日の時間の使い方という点ではいかがでしょうか。
町田:私は、執筆の時間を朝8時に子どもたちを学校に送り出してから、夕方6時までと決めています。それ以外はパソコンを開かない。全く書けない日もありますが、そういうときは無理して書きません。夜中まで書くと決めてしまうと、「どうしよう、今日はまだ一文字も書いていないから、少しだけ書いて寝よう」と焦ってしまう。それって自分を追い詰めるだけかなと。
また、私は取材やオンラインでの打ち合わせがある日は、一日中緊張してしまうタイプなので、そういう日も書かないようにしています。自分が何かに振り回されないような時間配分ですね。
張:「タイムマネジメント」だと、時間が主になってしまう。そうではなく「時間デザイン」をして、どうしたら自分が主になれるかを考えたいですね。
町田:自分を主にしたいのなら、できないものはできないと割り切ることも大事ですよね。
張:余談ですけれども、NHKの朝ドラ「ひよっこ」などの脚本を手掛けられている脚本家の岡田惠和さんが、忙しいときほど手帳のスケジュール欄に書くことがなくて真っ白なんだと言っていました。なぜならば、一日家にいて作品を書いているから、時間に縛られずに過ごす時間は、真っ白なんですね。
町田:確かに1日ずっと書こうと思ったら、予定は入れられないから、手帳は真っ白になりますよね。
張:でも、「タイムマネジメント」になると、手帳の予定は埋まっていなくてはいけないという悪しき既成概念があるんですよ。「時間デザイン」は、そうではないというメッセージでもあるのです。手帳の予定が埋まっていればいいのではなく、いかに自分が充実した時間を過ごすかが大事なんだよと。
町田:そうだと思います。私もボーっとしている時間に、なにか構想をまとめているのだと感じます。それが発露して文章に変わるまでの時間、つまり手帳が真っ白な間も、何か生み出しているんでしょうね。
でも、さすがに昨年は「白紙から立ち上がれ」動画ではないですが、私もどれだけ予定を消しただろうかと。去年の手帳を見返してみると、例年、子どもの行事などでだいたい週末は予定が埋まっているものですが、横線が引いてある。予定がキャンセルになって、子どもも寂しそうな顔していたなあって。
張:動画は、弊社のCMですけれども、こんな時代だからこそ、社会を少しでも元気づけたいと思っています。それこそ背中を押してあげたいですね。
町田:先の予定が一つでもあると、それだけですごくワクワクするじゃないですか。手帳に予定を書き込むということは、うれしいことだったんだなって気がつきました。
自分が誰かの背中を押して、
元気のお裾分けができる作家に
張:今後どのような作品を手掛けていきたいとお考えですか。読者へのメッセージなどがありましたらお願いいたします。
町田:先ほどお話した母と娘もテーマですし、あとは生と死。死別というのは、作家としてこれから長く書いていきたいテーマだと思います。『52ヘルツのクジラたち』もそうなんですが、私の話ってちょっと暗いんですよ。だから次は、「楽しかったな、私も明日頑張ろう」と思ってもらえるような、元気のお裾分けができて、明日の活力にしてもらえるものを書きたいなと思います。
張:楽しみですね。『52ヘルツのクジラたち』も、メッセージ性とエンターテインメント性のバランスがとれていて、重すぎなかったですよ。
町田:そうでしょうか。前の3作もそんなに明るくない作品だと感じているので、次はコメディでもいいから人を笑わせたいなって。これからも、読んでよかった、背中を押されたと思える作品を書き続けていきたいので、見守ってほしいと思います。
張:次回の作品も期待しています。今日は、ありがとうございました。

拝啓 あの日の自分
氷室冴子さんの訃報を知ったときの自分へ
氷室冴子さんの訃報を知ったとき、本当に自分が嫌いになったんです。いままで何をやっていたんだろう。もう取り返しがつかない、って。でも、決して遅くはないんだよ、頑張れば這い上がって作家になれる、大丈夫だよと言って、背中を押してあげたいですね。
実は、始めての作品を上梓したとき、氷室さんのお墓参りをして、墓前で「作家になりました!」って報告できたんですよ。そういう機会も巡ってくるよって言ってあげたいですね。
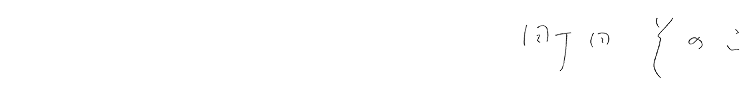
※この記事は【時間デザイン研究所】に掲載されていた記事を転載しています。内容は掲載当時のものです。








長脛彦 さん
自身,小学生の頃「いじめ」に遭ったことがあり,海洋生物について調べていて「52ヘルツのクジラ」を知り,自分の母親のようではなく自分のまんまで親になり,子育てで「虐待問題」に関心をもって,憧れだった氷室冴子の訃報を知って,大塚国際美術館の原寸大美術作品の森を彷徨って…人生と世界の綴れ織りのようにして作品世界が豊かになっていくんですね。
『52ヘルツのクジラたち』を読んで感銘を受けたという子どもを知っています。彼もいじめや虐待を受けて育ち,読みながらクジラの歌を聴いていたのでしょう。