時間〈とき〉ラボ運営事務局 さん

時代遅れのお酒として、国内では長らく販売が低迷していたウイスキー。しかし近年、その需要は回復し、市場は活況を呈している。そんななか、高品質で個性的なウイスキーを生産し、ジャパニーズウイスキーを世界に誇れる存在に引き上げたのが、埼玉県秩父市で「イチローズモルト」を生産する肥土伊知郎氏だ。イチローズモルトはいかにして世に送りだされたのか。そしていま、どんな思いでウイスキーづくりを続けているのか。秩父蒸溜所でお話を伺った。
肥土伊知郎(あくと・いちろう)
株式会社ベンチャーウイスキー代表取締役社長。1965年、埼玉県秩父市生まれ。実家は江戸時代創業の蔵元、肥土本家。東京農大醸造学科卒業後、サントリー勤務を経て、父が経営する家業の造り酒屋に入社。しかし、会社が2004年に他者に経営譲渡されたため、廃棄予定のウイスキー原酒を買い受け、ベンチャーウイスキー社を設立する。2008年2月、秩父蒸溜所が完成。2012年2月、自社で蒸溜した最初のモルトウイスキー「秩父 ザ・ファースト」はジャパニーズウイスキー・オブ・ザ・イヤー(米国の専門誌主催)を受賞した。
聞き手:日本能率協会マネジメントセンター 代表取締役 張士洛
家業を継ぎ、ウイスキーの魅力に目覚める

張:ご家業は日本酒の蔵元だったと伺っていますが、あえて洋酒のウイスキーづくりを始められた理由は何でしょうか。
肥土:私の実家は1625年に創業し、江戸時代からこの秩父でずっと造り酒屋を営んでいましたが、昭和の時代になってから、祖父が日本酒以外のお酒も生産しようと考えたようです。そのなかの1つのカテゴリーがウイスキーでした。昭和16年に埼玉県羽生市に新工場を建てて生産を始めたのですが、やがて戦争が終わり、日本に進駐軍がやってきたときに、彼らを相手にした洋酒の需要が増えるだろう見込んでのことではないかと思います。
その後、1980年代に入ってからは本格的なポットスチル(銅製の蒸溜釜:写真)を導入して、自社製のシングルモルトウイスキー(※)の生産を始めました。

張:なるほど、進駐軍向けにとお考えになったのですね。その後、高度成長期にかけて日本人もウイスキーを飲むようになりましたが、イチローズモルトが出回り始めた時期は、ウイスキーというお酒は、やや時代遅れのイメージもあり販売が低迷していましたよね。そうした逆風のなか、あえてウイスキーに賭けようとした理由は何でしょうか。
肥土:実は、私が実家に戻り家業を継いだ4年後の2004年に、経営難で会社が人手に渡ってしまいます。ところが、新しいオーナーさんはウイスキーには関心がなく、事業からの撤退を打ち出しました。ウイスキーの国内市場は、2008年まで縮小し続けていましたし、熟成に時間がかかる、樽を保管する場所が必要ということも合わせて考えると、無理もない話です。ただ、祖父が始めた羽生の蒸溜所には、1980年代に生産されて20年近く熟成を重ねていた原酒のストックが400樽もあったのです。
ウイスキーを選んだ理由は、私自身が純粋にウイスキーやバーの魅力に引き込まれたということもありますし、もちろん、羽生で20歳まで育った我が子のような熟成樽を簡単に見捨てるわけにはいかない、何とかしたいという思いが強くありました。
張:ウイスキーやバーの魅力に引き込まれたとおっしゃいましたが、どんなところに興味を感じたのでしょうか。
肥土:本格的にウイスキーの魅力に引き込まれていったのは、家業に戻ってからのことです。私は大学卒業後、ウイスキーづくりがしたくてサントリーに就職したのですが、配属先は企画部で、ウイスキー自体も売れてはいなかった時代だったので、いまほどその魅力に気づいていませんでした。家業を継いだとき、ウイスキーの樽のことを思い出して、従業員に話を聞いてみると、「うちのウイスキーは癖があるから売れませんよ」と、渋い反応でした。しかし試しに飲んでみると、たしかに癖があって個性は強いけれども、非常に面白いというか、何かの可能性を感じました。ただし、自分では面白い、可能性があると思っても、客観的にみてどうなのか、そして市場性があるのかという判断はつきませんでした。そこで、都内の有名なウイスキーバーを巡って、バーテンダーさんに評価してもらおうと思い立ったのです。
張:樽の中で眠っていたウイスキーが、20数年の時を経て、外の世界へ出たというわけですね。客観的な評価はどうでしたか。
肥土:一軒一軒バーを回って、お店のマスターやバーテンダーにテイスティングしてもらったのですが、「面白いね」「リッチな香りだ」「個性的」と、軒並み高い評価でした。そんなことを重ねているうちに、自分自身も、さまざまなウイスキーに接する機会が増えていきました。すると、特にシングルモルトウイスキーといわれるものは、ボトルごと、蒸溜所ごとに全然香りや味が違うということに驚かされました。ウイスキーにも、ワインのように産地やビンテージの違いを楽しむことができる。そういう魅力ある世界が広がっていたのです。
張:スナックで出される水割りにはない、別の世界があった。そこに可能性を感じたのですね。
肥土:スコットランドの蒸溜所のなかには、たったの3人で生産しているところがあったんです。そこのボトルが、遥かに遠く離れた東京の小さなバーに置いてある。そんな小さな蒸溜所がつくったものでも、個性的でおいしければ、こうやって飲んでくれる人がいる。それがウイスキーなんだと感心したのです。当時、ウイスキーの市場はたしかに低迷していましたけれども、バーに行くと、それなりのお年の方も、若い女性の方も、「スモーキーだね」とか「こんな違いがあるんだね」なんて言いながら、目をキラキラさせて、興味津々で飲み比べている。そこで、ウイスキーの可能性に気づかされたと同時に、自分自身がシングルモルトの魅力に引き込まれてしまったのです。
張:ちなみに、当時よく足を運んだ都内のバーはどちらでしょうか。
肥土:最初に足を運んだのは、南青山にある「ヘルムズデール」というお店です。いわば英国のパブのような、ビールも料理もおいしくて雰囲気のいいお店です。ウイスキーの品ぞろえも豊富で、愛好家にも古くからよく知られたお店です。その他、いわゆるウイスキーバーというカテゴリーでいうと、自由が丘の「スペイサイドウェイ」、有楽町の「キャンベルタウン・ロッホ」、そして都心からは少し離れますが、十条の「アルビオンズバー」、西川口の「カスク アンド スティル」にもよく行きました。
張:イチローズモルトをいただくなら、どこのバーがおすすめでしょうか。
肥土:銀座の「KAGE」、神田の「GROOVY」や「エクリプス ファースト」といったお店は、イチローズモルトの品揃えが充実していますよ。
張:それだけ毎晩バーに足を運ばれたということは、悪い言い方をすると、飲み屋に入り浸っていたともいえますね(笑)。
肥土:まさにそうです(笑)。父の会社では、例えば、紙パック入りの日本酒とか、ペットボトル入りの焼酎とか、量販的な部門で売上を伸ばそうとしていたので、夜な夜な、ウイスキーのボトルを抱えてバーに出かける私をみて、「跡継ぎのバカ息子は、戻って早々何やっているんだろうね」なんて、後ろ指さされたくらい(笑)。ですから、昼間仕事しているときは、ウイスキーの生産や販路開拓のための仕事に割く時間は、ほとんどとれませんでした。
張:結果的に、羽生にあった貴重な原酒の受け入れ先はどのようにして決まったのですか。
肥土:原酒の樽をどうか預かってほしいと、いろいろなところに交渉しました。しかし、当時ウイスキーはただでさえ売れていなかったので、どこも極力在庫を減らしたい。そんなときに人様の原酒を預かるなんて到底できない、という回答がほとんどでした。ところが、福島県郡山市にある笹の川酒造さんだけは、事情を説明すると、それはいちメーカーだけでなくて業界の損失だと。もっというと長い時間をかけて熟成させたものを廃棄してしまうのは、「時間の損失」だと。それなら、うちの倉庫を使いなさいと。そうして、貴重な原酒は廃棄を免れたのです。
張:まさに、「捨てる神あれば、拾う神あり」ですね。
※シングルモルトウイスキー
グレーン(トウモロコシ、ライ麦、小麦などの穀物)でつくったウイスキーをブレンドせずに、モルト(大麦の麦芽)だけを使用してつくったウイスキーのこと。
販路なし。口コミで広まったイチローズモルト

張:そして、いよいよご自分の会社を立ち上げて、まずは笹の川酒造さんに預かっていただいた原酒をもとに「イチローズモルト」の販売に乗り出すわけですね。最初はどのような売り方をされたのですか。
肥土:「イチローズモルト」というブランドの最初のウイスキーは、2005年に1本あたり1万3500円(税別)という価格設定で、600本ボトリングしました。品質には自信はありましたが、販路がまったくありません。当然、イチローズモルトというブランドはまだ無名ですから、小売りの酒屋さんに卸しても、たぶん店の片隅で埃をかぶってしまう。でも、ブランドがなくても味で評価してくれるのであれば、やはり専門店、つまりバーだなと思いました。そこで改めてバーを一軒一軒回って紹介していったのです。そして今度は、夜だけでなく昼間も卸の酒屋さんを訪問して、「あの店のバーテンダーさんのお墨付きですから、1ケース買ってください」というふうに交渉したのです。
張:またしても、バー巡りを始めたわけですね(笑)。ただし、昼間は酒屋さんにも営業をかけたと。
肥土:バーテンダーさん御用達の酒屋さんというのは、ウイスキー好きの人も多く訪れますから、「このウイスキーってどうなの?」っていう話になりやすい。すると、口コミで他店のバーテンダーさんにも広がっていくのです。また、バーというのは横のつながりが強い世界で、バーテンダーさんの仲間や先輩・後輩のお店をどんどん教えてくれるのですよ。そういうところも面白いですね。時間をかけて売っていきましたから、最初の600本を売り切るのに、丸2年以上かかりました。でも、そうやって地道に取り組んだことが、取扱い店舗の増加につながったという気がしています。
張:大口の消費というよりは、プロ同士の口コミで、じわじわと広まっていったということですね。そして、表彰を受けたことがきっかけで、ブレイクしたと。
肥土:そうですね。その後、カードシリーズというボトルを発売したのですが、これは、原酒を4つの異なる樽で寝かせたウイスキーをシングルカスク(※)でボトリングしたものです。同じウイスキーでも、樽によってこんなにも違いがあるということをシリーズのコンセプトにしていたのですが、バーで出会ったデザイナーさんとディスカッションするなかで、そういえばトランプって絵札が4種類だからラベルにちょうどいいよね、という話になりました。当時はバーに並ぶお酒のラベルに派手なものはあまりなかったので、お客様のほうから「あのトランプは何?」って聞いてくれるようになったのです。ただし、値段が高かったので、そうたくさんは売れませんでした。ところが、その中の一本が、ウイスキーマガジンという専門誌の「プレミアムジャパニーズウイスキー特集」という紙上コンテストで、最高の賞をとってしまったのです。世界中に読書がいる雑誌なので、そこから、「聞いたことないけれど、イチローズモルトって何だ?」と話題になったのです。それが2006年のことでした。
※シングルカスク
単一の樽(カスク)からとったウイスキーだけをボトリングしたもの。
ウイスキーの99%は時間が生み出すもの

張:樽で寝かせた年代物ほど価値が出るウイスキーは、まさに時間が生み出す贈り物ですよね。今回は「時間デザイン」がテーマですので、時とウイスキーの関係についても伺いたいと思います。
肥土:ウイスキーの製造工程そのものは、どこの蒸溜所もほとんど変わりません。ただ、そこに加わる大きな要素は、おっしゃるとおり、「時」です。人間がかかわって原料のモルトからウイスキーの原酒ができるまでの期間というのは、せいぜい1、2週間です。ところが、それを樽に入れてから、製品として出荷できるようになるまでには何年もの年月を要します。ですから、99%は時間によってつくられるといってもいいでしょう。なおかつ、ウイスキーの熟成に必要なオークの樽をつくるのに必要な木の成長期間を考えると、さらにかかります。例えば、10年もののウイスキーであれば、熟成期間の10年だけでなく、樽に使われる木の成長期間も含めた100年以上の時の恩恵をいただいていることになります。
張:そうか! 樽に入れて寝かせている期間のことしか頭になかったのですが、そこには樽の材料となる木そのものの成長期間も含まれるのですね。そんなウイスキーの製造工程のなかで、とくにこだわっている部分はどこでしょうか。
肥土:どこか1つの工程だけのこだわりというよりも、各工程における微妙な調整や工夫の積み重ねが、最終的には大きな差になって現れるのだと思います。例えば、ウォッシュバックという麦汁の発酵槽は、多くは金属でできていますが、秩父蒸溜所ではミズナラ材を使用しています(写真)。その理由は、木を使うことによって発酵槽の中で乳酸菌の育成を促し、樽の中で熟成するウイスキーをより華やかに、複雑な味わいにさせるからです。麦汁を蒸溜するポットスチルの形状についても、立地的にも予算的にも大きなものを入れる余裕はなかったという事情はありますが、小さなもので蒸溜すると、私たちがめざすヘビーでリッチな、飲みごたえのあるウイスキーができるという傾向があるのです。


自分なりのウイスキータイムを

張:先ほどからも、「熟成」が大きなキーワードとなっていますが、ウイスキーの熟成について、肥土さんご自身はどう捉えていますか。
肥土:時間デザインのコンセプト「“Time is Money”から“Time is Life”へ」というのを拝見して驚いたのですが、私の座右の銘は「時は命なり」なんですよ。そして、弊社の社是が「時とともに成長する」です。これは、ウイスキーづくりそのものが時をかけなければできないものだからということ、そして自分も含めて従業員は、成長できなければ時間の浪費に過ぎないという思いが込められています。そういう意味ではまさに、熟成すなわち時間とは、人間にとってもウイスキーにとっても「命」なんだろうということですね。
張:素晴らしいですね。私たちが打ち出そうとしていることを、すでに実践されています。それと、肥土さんは都内でサラリーマンをされていたわけですが、活動の中心を秩父に移されてからは、時間の流れ方という点ではいかがでしょうか。例えば、時計が刻む時間は一緒でしょうが、感じる時間というのはだいぶ違うのではないでしょうか。
肥土:秩父で過ごす時間は、やはり都会よりもゆっくりですね。それと、ウイスキーづくりを始めてからは、時間軸が長く感じるようになりました。今日仕込んだウイスキーが熟成する10年後にどうありたいと未来を思い描く、そのために今をこう生きる。そういう見方ができるようになりました。
張:本質はそこですよね。都会にいても、秩父にいても、10年後のことを考えながら生きている人は、時間デザインもできているのでしょう。でも、都会でビジネスをしていると、一年どころか半年先のことも見通せない。時間に追われて余裕がない人たちがほとんどだと思います。それを変えたいというのが、時間デザインのねらいでもあります。
肥土:ウイスキーには、時間を超えたロマンがありますよね。グラスに注がれた琥珀色の液体は、100年前と同じ製法でつくられていて、100年成長した木を使って10年間樽で寝かされて、いま、あなたと向き合っている。そんな思いでゆっくりとウイスキータイムを過ごして、時間に追われて疲れた心と体を癒していただければと思います。
張:そういう意味では、都会で働き暮らす人も、さっき教えていただいたようなバーなどで、リッチなウイスキータイムを過ごしていただけるといいですね。
肥土:ウイスキーは、アルコール度数が高いので、とっつきにくいイメージをもたれる方もいらっしゃいますが、いろいろな飲み方ができるお酒でもあるので、自分に合った飲み方を見つけて楽しんでいただければと思います。
張:地元産のモルトを使ったウイスキーづくりにもチャレンジしているとも伺っていますが、今後の夢などもお聞かせいただけますか。
肥土:大きなプロジェクトとしては、いま第二蒸溜所を建設しており、2019年中の稼働をめざしています。とにかく丁寧に、自分が、そしてウイスキーを愛する人が飲みたくなるようなものづくりをしていきたいですね。正直であり、決して嘘がない、時間をかけた真摯なウイスキーづくりというか。そしてゆくゆくは、30年もののウイスキーを皆さんと一緒に酌み交わしたいですね。
張:そう考えると、ワクワクしますね。私も、ぜひ一緒に30年もののウイスキーを味わえるように長生きしたいと思います。きょうは、ありがとうございました。
 秩父蒸溜所の倉庫で熟成の時を待つウイスキー樽。
秩父蒸溜所の倉庫で熟成の時を待つウイスキー樽。

拝啓 あの日の自分
家業が人手に渡ってしまった頃の自分へ
どん底という意味では、やはり江戸時代から続いてきた家業が人手に渡ってしまった頃のこと。だけど、いま振り返ると、辛かったというよりも楽しい思い出のほうが大きいかな。なんとかウイスキーをビジネスにつなげようと、日が暮れたらバーに行き、カウンターで自分のウイスキーや夢を語る日々。バーは自分にとっての職場であり、癒しの空間だった。私が夢を語ると、バーテンダーさんや周りの人がそれを応援してくれる。それが大きなモチベーションになって、また次の店に行って同じことを繰り返す。そうしているうちに、最初は先が見えない状況だったのが、「もしかしたら」という自信につながり、やがて確信になっていった。
あの頃の自分にかける言葉があるとすれば、「それで間違っていないから全力で前に進め」と。そして「夢を広げていけ」と。
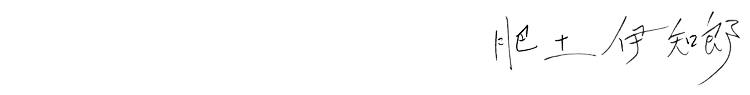
※この記事は【時間デザイン研究所】に掲載されていた記事を転載しています。内容は掲載当時のものです。



長脛彦 さん
日本酒の蔵元からウイスキーづくりに乗り出すというのは,まさに朝ドラ『マッサン』と同じですね。従業員にすら「癖があるから売れない」と言われた,引き取り手のない原酒を「面白い」と言ってくれるバーテンダーに一軒一軒売り広めて「イチローズモルト」というブランドを確立する。「時は命なり」…
ウイスキーやワインはそこに閉じ込められた時間〈とき〉を飲むときに解放する感覚がある。「命は時なり」…