時間〈とき〉ラボ運営事務局 さん

エジプト考古学者の河江肖剰さんは、ピラミッドの謎に迫るべく異分野・異業種のメンバーを掛け合わせたチームを結成し、3D計測などの最先端技術も駆使しながら発掘調査を進めている。その手法は、「神秘の秘宝」といったイメージが強かったピラミッドに、実証研究という新たな展開をもたらした。果たして、4500年前の彼の地では、どのような「時間」が流れていたのだろうか。
河江 肖剰(かわえ・ゆきのり)
1972年兵庫県宝塚市出身。高校卒業後、エジプトのカイロに単身で移住し、日本人専門の現地旅行会社で遺跡の観光ガイドを務める。その後、カイロ・アメリカン大学エジプト学科を卒業。大学4年の自主研究で、ピラミッド研究の第一人者である米国人考古学者マーク・レーナー博士のギザ台地マッピング・プロジェクトに参画。ピラミッド・タウンの発掘に従事。名古屋大学大学院人類文化遺産テクスト学研究センター共同研究員。2016年米国ナショナルジオグラフィック協会のエマージング・エクスプローラーに選出。米国古代エジプト調査協会調査メンバー。
聞き手:日本能率協会マネジメントセンター 代表取締役 張士洛
ピラミッドとは何か

張:ここのところ暑い日が続いていますが、今日は特に暑いですね。エジプトの暑さは日本と比べてどうですか。
河江:ちょうど先週エジプトから帰国したこところですが、ピラミッドの発掘現場は、じりじりと焼かれるような暑さですね。ギザのピラミッド周辺の気温は今の時期、40度を超えますが、湿度はそれほど高くありません。不快指数は湿気のある日本の方が高いかもしれませんね。
張:陽が落ちると涼しくなりますか。
河江:カイロは東京より人口が多いので、夜になっても都市が持つ熱気のようなものは感じますね。ただ、ピラミッドの周囲であれば、日陰に入るとすっと涼しくなります。
張:ではさっそくですが、ピラミッドはそもそも何を目的としてつくられたのか、といった辺りから教えていただけますか。
河江:ピラミッドは王の墓として建てられたというのが、多くのエジプト考古学者の考えです。ギザの大ピラミッドの建造は、古代エジプトの第4王朝時代(紀元前2543年頃~2436年頃)ですが、それ以前にも小規模のピラミッドがエジプトの地方に点在しています。
ピラミッドがつくられるようになったのは、エジプト文明の誕生から500年ほど経ってからです。5000年ほど前に国が統一され、その後、500年程の間に、国が落ち着き、資源や人が中央に集まる。権力者はそれらを用い、自らの強大さを広く知らしめるため、王権の象徴となる建造物をつくったのではないかと考えられます。そして、王の力が絶大なものとなっていく中で、王の埋葬もまた崇拝の対象になっていったのではないかと。
ただ、ピラミッドは王の埋葬だけでなく、太陽や星、オシリスと呼ばれる冥界の神の信仰など、神話的な意味合いも非常に強かったことがわかっています。なので、「王の墓」といってもそれは今日の私たちが想像するものとは異なる、その当時ならではの意味が込められているのです。
張:ピラミッドは当時の世界観や神話が集積された聖なる場所だったわけですね。
河江:私たち考古学者はコンテクスト(文脈、背景)を重視します。現代の感覚で「あれは王の墓だ」と片付けてしてしまうのではなく、4500年前のエジプトの王とはどのような存在で、その死や埋葬には一体どんな意味があったのかということを、さまざまな視点から丁寧に考えていかなければなりません。
張:神話とつながりがあるということは、その当時のエジプトの王は神とみなされていたということでしょうか。
河江:おっしゃる通りです。ちょうどピラミッドがつくられるようになった頃から、そうなったと考えられます。
すべての王が神とみなされていたのかは議論の余地がありますが、少なくとも古王国時代のクフ王とその父、スネフェルの2人は神とみなされていたと考えられます。長い歴史の中では、王が神の化身として崇められる時代が何度かあり、ピラミッドがつくられたのはその時代の一つだったのです。
ピラミッドをつくった人々

張:実現するのはなかなか難しいと思いますが、現代の技術を駆使してピラミッドをつくってみるのもおもしろそうですよね。
河江:実は日本の大手ゼネコンが、ピラミッドの建造を大真面目に計画したことがあるんです。建設費の総額を見積もったところ、1250億円になったとか。お金と時間さえかければつくること自体は可能だと思いますが、問題はつくった後に人々がそこに価値を見出して、それを数千年間、維持していこうと思えるかどうかでしょうね。
張:たしかに。ピラミッドの価値とは、あれだけの建造物がつくられたというだけでなく、それが4500年もの間維持されてきたところにあるわけですね。ピラミッドの建造にかかわったのはどのくらいの人数で、どのような社会的地位の人々だったのでしょうか。
河江:1980年代に私のボスであるマーク・レーナー(編注:アメリカの考古学者でピラミッド研究の第一人者)が大ピラミッドのそびえるギザ台地の南東に、ピラミッドをつくった人々の住んでいた街「ピラミッド・タウン」を発見しました。そこを調査した結果によると、恐らく2~3万人がピラミッドの建造に従事したのではないかと推測されています。
私はそのピラミッド・タウンの西の地区の調査を担当していたのですが、そこにはどちらかといえば位の高い貴族が住んでいたようで、ピラミッド・タウンで最大の邸宅が見つかりました。ピラミッド・タウンは、王宮だと思われる場所にも、一般人の居住していた痕跡があり、多様な人が住んでいたと考えられます。
張:そこでの人々の暮らしとはどのようなものだったのでしょうか。
河江:暮らしむきは総じて良かったと思われます。西の地区ではテンダーといわれる柔らかい子牛や野生のガゼルなどが食料として消費されており、一般の人が多く住む東でも、ヤギや羊が食べられていたようです。肉はとても貴重な食料ですから、当時の水準からすると、恵まれた暮らしだと言っていいと思います。
張:2~3万もの人が暮らせる街をつくるとなると、それだけでも一大事ですよね。
河江:先ほどお話したゼネコンによる「ピラミッド建造」の試算では、見積の第1項目が働く人たちの住居なんです。まずは働く人たちの住む場所を確保するというのは、当たり前のことのようですが、今までの考古学者にはない発想でした。「ピラミッドがどうつくられたか」という問いに対して、普通は「石をどう運んでどう積んだか」ばかり考えがちです。しかし、ピラミッドの建造がかなりの期間を要するプロジェクトであることを考慮すると、働く人たちの生活の基盤をつくることは、まず考えるべきですよね。
張:言われてみるとその通りです。それにしても、4500年も前の人が住んでいた街を発掘するというのは、本当に浪漫がありますね。
河江:時間を超えてその瞬間に立ち会うことはできませんが、実際の現場にいるからこそ、ビビッドに、生々しく感じるものはあります。土器には古代の人たちの指紋がついていることがあるのですが、そういうものを見ると、かれらとの距離がグッと縮まったように思えるんです。
古代エジプトの時間感覚

張:ピラミッドをつくった人たちの働き方はどのようなものだったのでしょう。仕事をしたり休んだり、というのはどうやって決めていたのでしょうか。
河江:実際のところわかっていないことが多いのですが、当時の1週間はどうやら10日間だったようです。そして、1年は今と同じ365日だったことが明らかになっています。
時間の捉え方についていうと、私たちの常識と大きく異なるのは、「時間は王だけが持っている」という点です。日本でも、天皇が崩御するか退位すると元号が変わりますよね。このもともとの意味は、土地だけでなく、時間も権力者が支配しているということです。
古代エジプトでも日本と同様に、王の治世年数が必ず記されます。王が亡くなると一つの時代が終わり、新しい王による新しい時間が始まるわけです。
張:王だけが時間を持っているというのは面白いですね。
河江:それと対比すると、現代では時間も民主化されていますよね。こうして私がインタビューにお答えする時間を工面するように、私たちは一人ひとりが自分の時間を持っていて、基本的には自由に使うことができます。でもそれは、古代の発想ではあり得ないわけです。
張:古代の人々の「オンタイム」「オフタイム」はどうやって決まっていたんでしょう。
河江:基準はやはり太陽でしょうね。太陽が昇ったら働き、沈んだら休む。どこの古代社会でも、太陽の動きと関連して時間を理解していたと思います。
エジプト人は太陽暦を生み出した民族として知られていますが、実際には太陽というより、ナイル川の氾濫に合わせた暦でした。氾濫期、種まき期、収穫期の3つの季節を知るために、恒星のシリウスを観察していたようです。シリウスの周期は太陽と同じく365日なので、結果として太陽暦が使われるようになった。彼らが知りたかったのは、太陽の位置ではなく、ナイル川の氾濫なので、むしろ農耕歴といった方が適切かもしれません。
張:時間を農耕の視点から分析するのも面白いですね。日本の二十四節気も、基本は同じですよね。人々の暮らしと密着した自然の周期を知るために暦が存在し、そのあとから日付がつくられる。
河江:太陽暦も後からいろいろな意味合いが付随して変わっていきますが、もともとは、自然のサイクルあわせて時間を決めていったんだと思います。
異分野・異業種のチームワークで謎に挑む

張:先生は実地調査による客観的な分析を重視されていますが、ピラミッドは従来、どのような手法で研究されてきたのでしょうか。
河江:これまでの調査では、定性的なアプローチが主でした。というのも、ピラミッドにはツタンカーメンの黄金のマスクをはじめとして、モノが大量に残されているので、研究者の意識がそっちに向かってしまうんです。従来の調査をたとえるなら、出てきたいくつかの証拠から「刑事コロンボ」が独自の推理を展開し、犯人を突き止めるようなやり方ですね。そうやって、各自が発掘したモノから思い思いの「推理」を働かせてきたせいで、包括的な記録作業がおざなりにされてきたんです。
そんな中で、全体をちゃんと記録し直そうしたのがレーナーです。ギザの地形や環境を綿密に調査し、仮説を立ててから発掘した結果、見つかったのが、先ほどの「ピラミッド・タウン」なんです。
張:なるほど。データをもとに仮説を立て、それを検証していくというのは、物理や化学といった自然科学にも通じるものがありますね。
河江:私たちが今やろうとしているのは、定量的なアプローチです。さまざまな角度から総合的にデータを収集し、そこから客観的に何が言えるのかを考える。まずは頑強な土台を築き、その上に論理を積み重ねていくイメージですね。
張:推理ではなく、データによって実証していくわけですね。そして、測量や画像などの技術の進歩によってそれができるようになったと。
河江:技術の進歩はもちろん大きいですが、「できるようになった」というよりは「できるようにしている」という感覚のほうが近いかもしれません。調査で何が最も大事になるかというと、コミュニケーションなんです。
私たちのチームのメンバーは、専門も年齢も国籍もバラバラです。考古学者は私一人しかいません。求めるものがそれぞれ異なるので、意見が食い違ったまま、平行線をたどることもあります。でも、私たちは絶対に諦めず、お互いが満足できるまで、とことん話し合う。もちろん時間はかかりますが、異分野の人間が協業するには、それしかないと思っています。
張:具体的にはどのようなプロセスで調査を進めていくのですか。
河江:まずは「今回の調査で何が知りたいのか」ということを考古学者である私が皆に伝え、それに対して各メンバーがそれぞれの専門分野からどんなアプローチが可能かを検討してもらいます。
どんなデータが必要なのか、課題があるとしたら何か、それにはどんな方法が有効なのか…といった地道なやり取りを何度も繰り返す。するとやがて、「謎」がはっきりとした輪郭をもつようになってくるんです。
正しく問えば正しい答えが見つかる、とよくいわれます。「何がわからないのか」がわからなければどうしようもありません。まずは謎をしっかりと形づくり、そこから、解くための方法を考える。その過程がコミュニケーションなんです。
張:それぞれの興味や関心が異なる中でチームをまとめ上げていくには、何がポイントになってきますか。
河江:どれだけ面白い謎を提示できるか、ですね。たとえば、考古学と工学と数学とでは、それぞれものの見方が異なります。私はよく工学の先生に、考古学と数学の間に立ってもらい、私の話を上手に解釈して「こんな問題があるんだけど解決できる?」と誘ってもらう。すると、数学の先生も「その問題は面白そうだ」と食いついてきます。調査がメディアで紹介されたりすれば、先生の家族や生徒も喜びます。すると先生の意欲も高まる。そうやって、さまざまな力を総動員していかないと、あの巨大な建造物の謎に立ち向かうことはできません。
張:メンバーの動機づけは本当に大切ですよね。最近の調査で何か具体的なエピソードはありますか。
河江:ピラミッドの精度の高い3Dデータを取りたいと思い、自分なりに戦略を考えて工学の先生に相談したんです。そしたら「それは戦略じゃなくて、ただの根性論だ」と言われてしまって(笑) そこで、作業を効率よく行うためには、どの場所に3Dレーザーを設置したらいいかを数学の先生に相談したところ、彼は数理的な計算を行い「この地点からこう取ればいい」という明快な回答を導き出しました。
最初は正直、「机上の論理ではないか?本当に大丈夫かな?」と半信半疑だったのですが、現場でその通りにしたらすごくうまくいったんです。仮に何か不都合があっても、現場からメールで相談するとすぐにフィードバックが戻ってくる。今まででは考えられないくらいの短時間で精度の高いデータを取ることができ、学界的にも注目されています。
張:まさに協業の成果ですね。
河江:昔はチームワークといっても同じ分野でした。でも今は異分野、異業種の掛け合わせです。文部科学省が2016年に「オープンイノベーション」を打ち出しましたが、私たちはもっと前から当たり前のように協業しています。だからそれを聞いたときは「へえ、そういう名称なんだ。気づくのが遅いな」と思っていました(笑)。
張:そのようなやり方で調査を進めるようになったきっかけというのは何かありますか。
河江:やはりレーナー先生の影響が大きいです。私は高校を卒業してから単身でエジプトに飛び、ガイドの仕事をしながら「いつかピラミッドの調査隊に加わりたい」と思っていたのですが、本当に運よく、レーナーの調査隊に参加させてもらうことができたんです。
レーナーの調査隊ではみんながフラットな関係でした。レーナーは何の実績もない私の意見にも素直に耳を傾け、正しいと思ったらちゃんと採用してくれました。そこには年齢も国籍も関係ありません。それにレーナーは誰よりも現場に足を運びます。あれだけの実績を残していれば普通は現場に来なくなるものですが、その姿勢や情熱からは今も多くのことを学んでいます。
張:素晴らしい師との出逢いがあり、多くの仲間と協業しながら4500年前の謎に挑んでおられるわけですね。これからもご活躍を期待しております。今日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

※この記事は【時間デザイン研究所】に掲載されていた記事を転載しています。内容は掲載当時のものです。


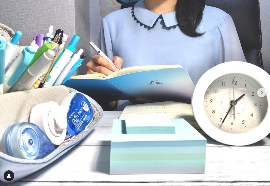



長脛彦 さん
1日と1年は地球の自転と公転で自ずと定まるが、そのあいだは任意に定めることができる。10進法から10日単位はわかりやすい。おそらく月の満ち欠けから28日単位の1か月を定め、それを4等分して1週間にしたのだろう。では六曜って何?