時間〈とき〉ラボ運営事務局 さん

古くは「ゲゲゲの鬼太郎」、最近では「ポケモン」や「妖怪ウォッチ」の大ヒットにみられるように、日本人は「妖怪大好き」民族である。今回は、日本文化研究の一分野として学問的に妖怪を研究する「妖怪学」を立ち上げた小松和彦氏に、妖怪と時間や空間の関係などについて聞いた。
小松和彦(こまつ・かずひこ)
1947年東京生まれ。文化人類学、民俗学者。大阪大学教授などを経て1997年に国際日本文化研究センター教授。2012年から同センター所長。2016年文化功労者。
聞き手:日本能率協会マネジメントセンター 代表取締役 張士洛
妖怪は「境目」の
時間帯に現れる

張:小松先生のご専門の文化人類学や民俗学の立場から、妖怪と時間の関係などについて、まずお聞かせいただけますか。
小松:1日を「昼」と「夜」という大きなくくりで考えると、昔の人は、基本的に明るい昼間は働く時間として捉え、暗闇に包まれる夜は仕事ができない休む時間としていました。そして、この昼と夜の境目にあるのが、夜明けと夕暮れという時間帯で、ここに妖怪が関係してきます。
夜明けや夕暮れ時のことを、「たそがれ時」とか「かわたれ時」といいますが、これは「誰(た)そ彼(かれ)」「彼(か)は誰(たれ)」というのが語源のようです。つまり、人の顔が暗く見分けにくい時間ということで、妖怪や人さらいといった社会の生活を脅かす者が現れやすい、人間にとって一番危険な時間ということ。そこに妖怪が関係しているというわけです。
張:境目の時間は、人間にとって危険な時間というわけですね。いまでも、薄暮の時間帯に交通事故の発生率が高いですよね。
小松:夜明けはともかく、夕暮れ時はどんどん暗くなっていきますから、特に子どもは早く家に帰らないと道に迷って危険な目に遭う可能性がありました。だから「妖怪が出るよ」とか「人さらいが現れるよ」と注意を促す意味もあったのでしょう。
日が沈んだ後、もっとも怖い時間は「丑三つ時」です。まさに「草木も眠る」時間帯で、人間にあらざる者がもっとも好む時間とされていますね。それは暗闇を意味するだけでなく、丑の刻から寅の刻へと変わっていく、陰陽道では時間的にも空間的にも鬼門にあたります。
張:夜明けと夕暮れという境目とともに、日本人が長い間使ってきた旧暦でいうと、満月や新月という境目はいかがでしょうか。
小松:旧暦だと大晦日が新月になりますから、そこから15日経った満月のときに小正月に行事をします。また、節分というのは、立春・立夏・立秋・立冬という4つの節気の前日にあたりますが、立春の節分には鬼が出てきますよね。これは節分が夕暮れと同じように季節の境目だからです。つまり今日で古い季節が終わり、明日から新しい季節が始まる。そういう意識のもとで象徴的に鬼を追い払う儀式をするのです。すると、鬼が古い季節の穢れを全部背負って出て行ってくれる。そうやって清めてから新しい季節を迎える。「ときをつくる」といってもいいかもしれません。
張:人間にとって鬼というのは、古い季節をリセットして新しい季節を迎えるために、どうしても必要だったのですね。
小松:そうです。鬼に来てもらって穢れを持って行ってもらわないと困るのです。ただし、居座られては困るのですが(笑)。ちょっと屈折していますが、人々の持っている穢れを持って行って、そのうえで退散してくださいと。また、鬼という存在は別に見えなくてもいいのですが、見えたほうがわかりやすい。ならば象徴的にお面をかぶった人を鬼に仕立てて追っ払おう。そういうふうにして演劇的な行事に変わっていったのです。
自然観察から得られた時間

張:ところで、妖怪にも寿命があって、死ぬこともあるのですか?
小松:妖怪は死なないわけではないのです。たとえば、浦島太郎が連れていかれた竜宮城は、不老不死のように描かれていますけれども、地上の300年が3年に相当するというだけで、地上から見れば、時間がゆっくり流れているということです。そういう時間観念があるというだけで、竜宮城に住んでいる人が死なないわけではありません。
張:死なないと、妖怪は退治できないわけですからね。
小松:ただ、魂について考えると難しいですね。退治された後も魂を鎮めるために祀るのですが、100年経て魂も滅びるだろうから神社を取り壊そうというわけにはいかないのです。封じ込められても、何らかの形で存在し続けると考えられることが多いのです。
張:どこかで肉体を得て、また復活するということもあるでしょうしね。でもそうすると、退治しきれないですね(笑)。
小松:そうでもないのですよ。たとえば、九尾の狐(※1)は殺生石のなかに封じ込められた魂を、お坊さんが来て輪廻から切り離して成仏させるのです。それをしないと六道の間をまた転生してしまう。戒名を与えて供養し成仏することによって、魂は我々の世界と関係した六道(※2)から一応外れてくれる。そういう、なかなかよくできた話ではあります。
※1九尾の狐:9本の尻尾をもつ狐の妖怪。
※2六道:天道、人道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道という、輪廻転生の6種の世界。
張:浦島太郎の話とは逆に、狐の時間は進み方が早いといいます。これはどうしてでしょうか。
小松:狐の一生は人間よりもかなり短く、10年以内でしょう。となると、狐から人間を見た場合、3年が300年にも見えるということです。セミも同じですね。人間から見たらとても短い寿命ですが、セミからすれば当たり前ということです。
張:まさに「象の時間、ねずみの時間」ですね。この時代にそういう発想があったんですね。
小松:自然を観察することによって得られた感覚なんでしょうね。セミのように、たとえ一週間で死んでいくようなものであっても、それはそれで有意義な一生なんだよ、ということを教えられている気がしますね。そうすると、人間も不老不死の仙人になるよりも、人間としての時間を精一杯生きることが大切なんだと言えるのではないでしょうか。お嫁に行ったらその家のしきたりに従えとか、郷に入っては郷に従えとか言いますが、そういう考え方が比喩的に用いられているようにも思えます。まさに「時間デザイン」にもつながっていると思います。
張:自然観察によって、時間と空間を捉えているのですね。
小松:そうですね。別のたとえでいうと、農民が自分たちの農作業を考えたときに、いつ種をまいたらいいのか、というのはかなり重要ですよね。そのためには、周囲の草木の成長や、気象や天体の動きを見てタイミングを測っていたんだと思います。つまり共同体全体で、自然や天体の運行という空間の変化の中に時間を見ていたのでしょう。
妖怪と日本文化

張:四季それぞれで、出てくる鬼や妖怪は変わるものですか。
小松:そんなには変わりませんね。ただ大きく分けて、鬼は冬に出てくることが多く、夏になると出てくるのは幽霊です。夏のお盆は、あの世から先祖を迎えて、そしてまた送り返すというものですが、良い先祖の霊ばかりでなく、恨みを持った悪い霊まで迎え入れてしまうことがある。そこで、夏に怪談物が流行るというわけです。子どもたちの夏休みに合わせて、妖怪や幽霊の企画展をやる美術館や博物館も多いですよね。ただ、最近は妖怪ブームで、年がら年中妖怪が出てきますけれども(笑)。
張:妖怪の認知度が上がったということは、研究者としては好ましいのではないでしょうか。
小松:長年妖怪を研究してきて思うのは、日本人の生活文化のなかに妖怪は深く根差しているということです。文学にも、芸能にも、民間伝承にも、そして最近ではゲームにも、あらゆるところに出てきますよね。これだけ生活文化に密着している以上、日本人はなぜ妖怪が好きなのか、その理由を学問としてきちんと考えてみなければならないと思ったのです。
張:つまり、妖怪のきちんとした研究を抜きにして日本文化は語れないと。
小松:そうです。いわば芸術性の高い文化ばかりを学問的に論じるのは間違っていると思ったのです。とりわけ庶民が語る妖怪は、芸術性としては低く見られてしまいがちです。しかしそれを却下してしまったら、ゆがんだ日本人像しか見えてきません。僕自身は、日本文化をきちんと考えていくために妖怪も学問的にきちんと位置付けたい。そのためには、学際的なアプローチがいいと思いました。それが現代の大衆文化につながっている可能性もあるし、新しいものを生み出す文化資源になっているかもしれないからです。さすがに、妖怪ウォッチみたいなものを売り出そうとは思いませんけれども(笑)。
張:クールジャパンを支えているのも、大衆文化やサブカルチャーですね。
小松:良い悪いは別としてそれが日本の文化なんです。聞くと、みんな妖怪は好きだというのですが、研究するというと笑うのです。B級だのC級だの、迷信の成れの果てだの、いろんなことを言われましたが、日本文化だから研究する意義はあるんだと主張してきました。
張:ご著者にも書いておられますが、日本人は目に見えないものを見える形にして新しい文化にしていく力がありますよね。
小松:妖怪といわれているものは、奇妙な現象に関するとりあえずの「説明」と捉えことができます。それを物語としてまとめたり、そのストーリーを語ったり、あるいは絵にしたりすることによって、ほかの人が追体験して妖怪文化が形成されていったのです。
張:日本人ならではのクリエイティビティの源泉は、もしかすると妖怪のような目に見えないものを具体的に描けるという能力なのかもしれませんね。
小松:中国や韓国からも当センターに研究者が来ますが、彼らは、日本人の妖怪の表現力は信じられないくらいだといいますよ。見えないものに対して、精緻に色まで付けて絵画にしていく力はすごいと。たとえば、「山海経」という中国の古い文献があって、妖怪などの絵もあるのですが、この本が日本に入ってくると、さらにリアルになっていくわけです。
屛風絵の「風神雷神」も、ルーツは仏教画ですが、俵屋宗達が芸術の域まで高めた。日本人の文化力の根底にはきっと見えないものへの造形力があって、それが現代まで続いているのだと思います。
妖怪と神の違い

張:また、ご著書で「人間が制御できるものが神、できないものが妖怪」とお書きになっていますが、この考え方についてお聞かせいただけますか。
小松:実は神も妖怪も根本は同じで、あらゆるものに魂を見出すアミニズムと呼ばれる一種の信仰形態に基づいています。日本人はその範囲をどんどん広げていきました。そして、同じ魂でも人間にとってプラスに働いてくれる和魂(にぎたま)と、災いというマイナスの形で働く荒魂(あらたま)という両極を見出しているのです。魂は、いったん荒魂になると、怨霊や祟りという形で人に災いをもたらします。それを鎮めるために、さまざまな儀式や行事が必要になるのです。これが、いわば「制御」ですね。
張:さきほどの九尾の狐のように、妖怪の持つ荒魂を封じ込めるということでしょうか。
小松:荒れる魂は封じ込めるだけでは不十分です。だから、何年にもわたって毎年お祭りするのですが、そうすることによって荒魂の恨みの部分がだんだん浄化されていきます。すると荒魂も和魂に変わっていきます。たとえば、京都の北野天満宮は、菅原道真公の怨霊、つまり荒魂を祀ったものですが、いまは和魂となり、学問の神様となっています。
張:長い時間をかけて祀れば、人間のために働いてくれるようになるということですね。
小松:そうですね。だから妖怪と神の違いは、きちんと祀られているかどうか。そして定期的に行事やお供えをするといった人間との間の約束が守られているかどうかです。河童を神様にしているところも、蛇を神様にしているところもありますが、要するにきちんと祀られているかどうかで、本質的に大きな違いはないのです。
日本人の心に宿る「異界」

張:現代人は、荒魂が和魂になったり、和魂が荒魂になったりするという考え方は、あまりしないかもしれませんね。
小松:貨幣経済が発達していくにつれて、さまざまなモノに魂が宿るというアミニズム的なものが失われていったのだと思います。お金さえ出せば、どこで誰がつくったかなんてあまり考えずにモノは手に入りますから。お金でモノを買うという行為自体が、モノに宿る魂を殺してしまったのです。
張:モノにも魂が宿るには、背景にあるストーリーが大切ということですね。
小松:ただ、それでも日本文化というものは、妖怪みたいなものを捨てきれないところがありますよね。現代でもお盆になるとご先祖様の魂が帰ってくるなんていうのは、身近なところに「異界」を感じている証拠ではないでしょうか。西洋の文化を取り入れて、新暦で時間を管理するようになっても、そういうところは捨てきれないでいる。妖怪も含めた異界をもう一度自分たちの生活のなかに現代的な観点で取り戻したいという思いがあるのかもしれません。
張:現代社会は、目に見えないものは信用しなくなっている。けれども、まだ踏みとどまっている状態でしょうか。
小松:人生って、常に浮き沈みがありますよね。社会も同じで、何か不安があると妖怪で表現しようとするわけです。いわば「心の表現装置」とでもいいましょうか。妖怪のことを本当に信じていようがいまいが、そんなことは関係なく、それでしか表現できない何かがあるんだろうと思います。
宮崎駿監督は、妖怪は描くけれども幽霊は描きません。それはなぜかというと、幽霊は個人対個人な関係にとどまるのに対して、宮崎作品は、自然とか共同体といった大きなものがテーマになっているからです。だから、その自然や共同体に何か問題が発生したり、不安や脅威があったりすると、森の精や妖怪が出てくる。まさに表現装置ですよね。
張:ところで、先生が妖怪とか異界に興味を持つようになったきっかけは何でしょう?
小松:親しい友達にお寺の子どもがいたりして、幼い頃から「死」というものに対する感覚が敏感だったのでしょう。妖怪や怪物が出てくるような映画もよく観ました。もっと詳しく知りたくなって本を読み漁るようになると、そこには化け物もいるし、ガリバー旅行記のような巨人の国や小人の国がある…まさに異界ですが、そういう本を好んで読んでいるうちに、いつの頃からか、自分たちの住んでいる世界の向こう側の世界にあこがれ、畏れを抱くようになった。そしてある時に、研究者がいないということに気づいたのです。なぜきちんと研究しないのかと。民俗学では研究されていましたが、少し範囲が狭いなと。
張:子どものころからイメージを膨らませていった異界を自分で研究してみたくなったと。
小松:謎解きになるんですよね。自分で納得のいく仮説を立ててみたかったのです。調べている人がいても物足りない。百科事典をみても載っていないじゃないか。だったら自分で謎を解いてやろうと。
張:でも、異界にしても、妖怪にしても、答えはないというか、謎解きは難しいですよね。
小松:先ほども言いましたとおり、日本の場合はいろんな分野に妖怪がはびこっていますから、底なしですよね(笑)。でも、これだけ他の国からあこがれの対象となるような文化なのですから、僕はもっと国家的に予算を投じて、組織的に盛り上げてもいいのではないかと思っています。アニメの殿堂のような目に見えるものでなく、その元になっている妖怪のことをちゃんと掘り起こしていけば、将来の財産になるのではないでしょうか。
張:本当ですね。先生がすでにおやりになっているように、日本の誇るべき文化として守り、そして学問的な研究も含めて、きちんとした形でもっと発信していただきたいと思います。今日は、ありがとうございました。

※この記事は【時間デザイン研究所】に掲載されていた記事を転載しています。内容は掲載当時のものです。

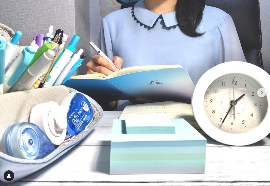


長脛彦 さん
見えないものを視覚化すれば共有できる。未来社会を実体化する大阪関西万博がいよいよ始まる。楽しみたい。