時間〈とき〉ラボ運営事務局 さん

日本人独立時計師のパイオニアである菊野氏は、ほとんどの部品を一人で作る。殊に鉄の棒を100分の8mmという髪の毛ほどの太さまで旋盤で削るなど、独立時計師のなかでもパーツまで手作りするのは少数派だという。自動化が進む現代で、アナログな手作りにこだわる理由とは。
菊野 昌宏(きくの・まさひろ)
1983年北海道深川市生まれ。高校卒業後、陸上自衛隊に入隊。2005年、自衛隊を除隊し、ヒコ・みづのジュエリーカレッジで時計づくりを学ぶ。卒業後も同校に研修生として残り、独学で機械式時計をつくり始め、3カ月後に不定時法を用いる和時計を完成させた。2011年、スイスの独立時計師協会(AHCI)に日本人で初めて準会員として入会、世界最大の宝飾と時計の見本市「バーゼル・ワールド」に初出展。2013年、AHCI正会員に昇格。2015年、和時計改(税抜1,800万円)を発表。
聞き手:日本能率協会マネジメントセンター 代表取締役 張士洛
現代人の時間感覚

張:江戸時代から明治初期にかけて製作された和時計を腕時計に再現し、時代を超えた挑戦を続けられる菊野さんの時間との向き合い方について、ぜひともお聞きしたいと思います。まずは分かりやすいところで、1日はどのようなサイクルで過ごしていらっしゃいますか。
菊野:時計をつくっている割に、きっちりした時間管理は実はあまり得意ではないんです。スケジュール管理は妻に任せていますね。いつ休むかも特に決めず、納期が近ければ長い時間働くこともありますが、たいていは余裕をもって製作にあたっています。単純に作業するだけでなく、調べ物をしたり、時計の新しい機構を実験したりする時間も含めて、だいたい1年間の納期をいただいています。
独立時計師の仕事は、時計をつくるばかりではありません。歴史を調べ、英語の論文を翻訳しながら解読するなど、時計づくり以外にもいろんな作業があります。だから面白い。現代社会が効率を追求して失った面白さをこの工房で味わっているといったところでしょうか。時計を通じて掘り下げていくと、それがまた時計づくりに返ってくる。自分の時間を犠牲にして、わが身を削りながらつくるより、いろんなことを楽しみ、その過程で得た経験も生かしながらつくる方が、いいものができると思っています。
張:1本の時計づくりにじっくり取り組まれるのですね。朝型、夜型などのリズムは特に意識していませんか。
菊野:集中できる時間帯も特に決まっていませんね。大切にしているのは毎日8時間以上寝ることです。しっかり睡眠をとって、心身の状態を保っています。あまり無理をしない方が、長く、安定して仕事をできますからね。
睡眠時間を削れば1日に仕事できる時間は確かに増えますが、時間の濃度は薄くなるのではないでしょうか。たっぷり寝て、集中して、仕事の中身を充実させる方が、結果的に良いと考えています。
張:私も、同じ時間を過ごすなら、1時間という「尺」ではなく、「濃度」を求めたいなと思っています。昨今の働き方改革もそういうことでしょうね。
菊野:定時制で仕事をするのにはきっと難しいところもありますよね。仕事の成果にかかわらず、それこそ濃い1時間も薄い1時間も同じ給料をもらえるわけでしょう。みんなが怠けてしまったら、とても効率が悪くなる。時間で区切ると管理しやすいように思えますが、その実、トータルで見たらどうなんだろうと疑問です。
張:働き方改革を進めている一方で、現代人は、時間にますます追い立てられているような気がします。
菊野:私は一人で工房にいることが多いので詳しくはわかりませんが、社会全体に、1分、1秒も無駄にできない、時間に対する脅迫観念のようなものを感じますね。例えば電車の中でも、誰もが一心不乱にスマホをいじっていてせわしないなあと。常にいろんな情報を取り込んで、誰かとつながっていないと不安だと感じる人が多いのでしょうか。私なんかは、何もせずにぼけーっと座っている時間も必要じゃないかなと思いますけどね。
張:一人でじっくり考える、そういう時間ですよね。
菊野:スマホもテレビも音楽も何もない、何もしない。ただぼぉーっとしていると、いろんな思考が浮かんで、新しいものが生まれるきっかけにもなります。そういう時間をもったいないと思わずにつくった方がいい。ミヒャエル・エンデの長編童話『モモ』は大人になってから読んだのですが、あれに出てくる「時間泥棒」の要素は確実に増えていますよね。昔は携帯電話がなくても何とかやっていたのにいつの間にか携帯電話が現代人の必須アイテムになって……。あれがない頃は時間に対してもっとおおらかだったんでしょうね。
張:日本は1873(明治6)年に定時法へ移行しましたが、かつての不定時法は、夜明けと日暮れを境に、それぞれを6等分して「一辰刻(いっとき)」と数えました。同じ一辰刻でも季節によって伸びたり縮んだり。日本人は江戸時代までずっと、不定時法のリズムで暮らしてきたのですよね。
菊野:農業中心の生活でしたから、お天道様が最も重要な指標だったんでしょうね。現代は「暗かったら電気をつければいい」と、日の出、日の入をあまり意識することはありませんが、昔は明かりの燃料が高価だったこともあって、太陽の光を最大限に活用していたのでしょう。もしかしたら今後、エネルギー問題が顕著になって、不定時法に戻しましょう、という時代が来ないとも限りません(笑)。
張:我々が意識して、不定時法の発想をもって、時間の使い方にメリハリをつけても良いかもしれませんね。菊野さんは自然体でそうされている。時間に縛られ過ぎている今の日本社会にとっては、すごく大事なことだと思います。
機械式時計の価値

張:時間を意識しても結果を出せず、だらだらと過ごしてしまう人もいるなかで、菊野さんはアウトプットとして、素晴らしい時計を製作されています。自動化できる部分があるにもかかわらず、あえて手仕事を選ぶ。そこにどんな価値を見出しているのですか?
菊野:時計づくりの自動化というと、電池で動くクォーツ時計がわかりやすいですね。あれだけ正確な時計を大量生産することで、今では百円ショップでも買えるようになりました。ものすごい技術の進歩で、工業製品の鑑です。にもかかわらず、その技術を評価して、愛着を持って一生使おうという人は多くありません。「安い製品は大したものじゃない」と、モノの価値が値段でしか見えなくなっているように思います。
どんなにすごい技術を駆使して、安くていいものをつくったとしても、買った人が満足を得られなというのは、なんだか皮肉ですよね。その一方で、ミリ単位のネジを人間の手で削るというと「すごい!」って思うじゃないですか。僕自身もそういう作業を楽しんでいるので、つくる過程を丁寧に伝えたくて、すべての工程をビジュアル化した本をお客様にお渡ししています。これがあれば、ものづくりのワクワクを共有できるかなと。

張:これはいいですね! 時計と一緒にもらったら思い出に残るし、嬉しいでしょうね。
菊野:完成品だけ見ても、つくる過程や作り手が込めた思いのすべては伝わりません。手作業、機械式、伝統的――言葉としてはいろいろ浮かびますが、具体的にどうしているのかを伝えたいんです。イメージだけで高級だと評されるのも何か違う。実際のやり方に感動し、その価値を納得してご購入いただきたいんです。この本を見れば完成までのプロセスが、ほかの工業製品とは明確に違うことがご理解いただけると思います。
張:いやぁ、素晴らしい。これこそ価値ですね。
菊野:買い物では、そのモノと値段しか見ていない人が多いですが、モノの背景にある物語にもっと関心を持ってほしいと思います。モノの値段を決めるのはほとんど「どうつくったか」ですから。同じ「メードインジャパン」でも、一方はほとんどを海外の工場でつくっておいて、最終の仕上げだけ日本なのかもしれない。消費者が考えなければ、つくり方は無視されて、効率の良いやり方しか残らなくなってしまいます。
今は作り手と使い手の距離が離れすぎてしまって、顔が見えないから、どうしても想像するのが難しいですよね。いろんなものが安く買えるようになったことで、便利さがいきすぎているような気がします。
張:便利なものがあふれているので、ありがたみがなくなっていますよね。戦後からしばらくの間は、必要なものが安価に手に入ることの重要性は高かったのでしょうけれど。
菊野:工場で自動生産した方が安くて質も良いのかもしれませんが、人間は不合理な生き物です。あまりに専門的になりすぎると、ありがたみが薄れ、満足できなくなってしまう。それが人の可能性であり限界でもあるかもしれません。
張:菊野さんの物語を理解しているお客様は、注文してから、完成までが待ち遠しいでしょうね。
菊野:お客様には「待っている時間も楽しかった」と言っていただきます。時計そのものというより、時間を買っていただいているのかなと。それは待っている時間だったり、完成品を見る瞬間だったり、時計と過ごす時間だったり……。毎日つけるという方もいますが、ここぞというときだけつけるという方もいらっしゃいます。そういうお話をお聞きすると、単なるモノを超えた存在として、向き合っていただけていると感じますね。
時計づくりに
たどり着くまで

張:菊野さんは、時計のほぼすべての部品をご自身でつくられていますが、一人でつくることにこだわるのは、どんな思いからでしょうか。
菊野:子どもの頃からものづくりが好きで、プラモデルやレゴブロック、工作に興じていました。まずは自分で何をつくりたいかを考え、それを基に設計図を起こし、材料を集めて、試行錯誤しながら、想像していたものを形にして、それを人に褒めてもらう。その一連の流れに魅力を感じていたように思います。
ものづくりはずっと大好きだったのですが、高校生になって進路を考えたとき、例えば一台の自動車を一人で全部つくることはできないじゃないですか。構想、設計、デザイン、部品、組み立て……。エンジンを一つ作るのにも、かなり細分化されています。効率を求めた結果なのでしょうが、それはちょっとつまらないなと思ってものづくりの道はあきらめ、自衛隊に入りました。
張:自衛隊ではどんな仕事をされていたのですか。
菊野:僕は小型の銃の整備を担当していました。何年もいれば、いずれは戦車や大砲といった大きなものを任されていたかもしれません。
張:自衛隊にいるときに時計に興味を持つようなきっかけがあったのですか。
菊野:あるとき上司に何十万円もするオメガの時計を見せてもらったんです。そこで初めて機械式時計というものの存在を知りました。当時、自衛隊の売店で買った1,000円くらいのデジタル時計をしていた自分には、そんな高額の時計があること自体が驚きでした。その後、本屋で偶然機械式時計の雑誌を見つけて、内部の機械の写真に魅せられたんです。こんなに精密できれいなものが直径3cmほどの中に詰まっているのか、これはすごく面白そうだなと。
そこから自分でも機械式時計を買うようになり、時計の中身への興味がどんどんわいてきた頃に、部品の削りだしから組み立てまでを一人でやる「独立時計師」の存在を知ったんです。時計は一人でつくれるんだってわかると、いてもたってもいられなくなり、自衛隊を辞めて、機械式時計の修理を学ぶことができる渋谷の専門学校へ行きました。
張:時計がつくりたかったというより、一人でつくれるから時計を選んだ?
菊野:そうですね。時計自体も魅力でしたが、一人でものづくりを全部できる点が面白そうだなと。自衛隊はチームで動くから、ある意味、個を殺す必要がありましたから。もちろん、それはそれでとても大切なことを学びました。
張:なぜ普通の時計ではなく、不定時法など、日本独特の暦に関心を持たれたのですか。
菊野:時計づくりを学べば学ぶほど、その難しさを思い知らされました。専門学生のときに、日本のメーカーやスイスの工房に何千万円もする機械があるのを見て、これを個人でそろえるのは無理だなと。それに、スイスでは時計の産業構造が水平に広がっていて、歯車、ケース、文字盤と分業化されていますが、日本では各メーカーが全部つくっているんです。その環境の違いを見て、「だから日本には個人で時計をつくる人がいないのか」と妙に納得してしまいました。
諦めかけていたとき、たまたまテレビで、芝浦製作所(後の東芝・重電部門)の創業者である田中久重がつくった「万年時計」のドキュメンタリー番組を見たんです。衝撃を受けました。コンピュータも工作機械もない江戸時代に、歯車を一つひとつヤスリで削って、こんな精密な時計をつくった人がいるのかって。だったら、はるかに恵まれている自分ができないというのはただの言い訳じゃないか、できるかどうかわからないけど、まずやってみようと思ったんです。それで国立博物館に行って万年時計のレプリカを見て田中久重の情熱を受け取り、専門学校の設備を使わせてもらいながら、時計づくりに挑戦しました。
独立時計師になるまで

菊野:田中久重の万年時計は構造的に立体的なスペースが必要で、そのメカニズムのまま腕時計のサイズにするのはちょっと無理でした。でもあるとき、和時計の不定時法表示を自動化した論文をネットで見つけて、直感的に「これなら腕時計にできるかもしれない」と思いました。それを小型化したものが、2011年に発表した和時計です。構想から完成までは意外と早かったですね。熱に任せ、がむしゃらになって、3カ月ほどでつくりました。
張:スイスの著名な独立時計師であるフィリップ・デュフォー氏にお会いしたのはその後ですね。
菊野:専門学校で講師として働きながら、学校の設備でつくり続けていましたが、当時は先が見えない状態でした。たまたまデュフォー氏の通訳を務める方が学校に遊びに来られて、「面白い時計をつくっている日本人がいる」とデュフォー氏に紹介してくれたんです。スイスのアトリエに誘われ、過去につくった時計や製作過程の写真を持参しました。デュフォー氏には「とても限られた環境でよくやっているね」と褒めていただきました。そして来年の「バーゼル・ワールド(編注:スイスのバーゼルで開催される世界最大の時計と宝飾の見本市)に出展してみないか」と誘われたんです。
そのときは正直言って、自分が売れる時計をつくれるという自信がなく、一瞬躊躇しました。でもここで断ったら二度とチャンスはないと思い直して出展を決めたんです。
張:その当時は既に、機械式時計をつくる技術を体得されていたのですか。
菊野:いえ、まだまだでした。歯車を自分でつくるようになるのはもっと後で、当時はできるところから、という感じです。最初の和時計は、他の人のアイデアをただ小さくして腕時計に入れただけなので、注文も取らずにそのまま寝かせていました。和時計ができたことは嬉しいけれど、やっぱり自分のオリジナルじゃない。これでは田中久重には認めてもらえない。もっといい仕組みが思いつくまで、和時計は封印しようと思ったんです。
張:ストイックですね。それでまた違う時計をつくるようになっていったのですね。
菊野:2011年のバーゼルに出典した和時計は二層構造で、普通の時計部分に和時計機構を重ねて不定時法を表示するので、どうしても分厚くなってしまうんです。それをどうにかできないかとずっと考えていました。2014年、新たに構想し、秋ごろから作り始めて、2015年3月にようやく「和時計 改」を発表しました。上半分に時計機構の歯車などを、下半分に不定時法機構を凝縮して重ねています。裏側に365日で1周する針で、二十四節気も表示します。ようやく自分の時計が作れた気がしました。
張:せっかく作ったのに売らなかった時計もあるとお聞きしました。
菊野:複雑なからくり時計なんですけど、鶴の動きと鐘の音がどうしても納得いかなくて……。それをつくるのに1年3カ月もかかったのでその年は経済的に大変でした。妻には本当に迷惑をかけましたね。
張:時計の中の部品なんて普通は見えないのに、一つひとつ丁寧に磨くのはなぜですか。
菊野:将来、メンテナンスでこの時計を分解する時計職人のためです。こんなところまで磨いてるんだって思ってほしくて。使う人にはわからないですけれど、田中久重の万年時計のように、後世の人を仕組みやクオリティで驚かせたいんです。
五感をフルに生かす

張:先ほども少しお聞きしましたが、現代人の時間の使い方を見て感じられることはありますか。
菊野:ものすごく便利に、効率的になった一方で、それがあまりにも当たり前になってしまって、ちょっとでも不具合が生じるとイライラする人が多いと思います。それは技術の問題というより、人間の問題ですよね。
機械式時計は、五感で感じられるシステムです。歯車が回っているのが見えて、チクタクと音が聞こえる。電子は目で動きを追えず、動く音もなく、脳でしか理解できない。そこに人が共感するのは難しいと思うんです。専門家にしかそのすごさがわからない。そういうものが世の中にあふれすぎて、当たり前にいいもの、素敵なものを純粋に感じられなくなっている。
朝起きたときに「いい天気で気持ちがいいな」みたいに、人間って、もっと単純なことでも喜べたり、楽しめたりすると思うんです。もっと感覚を研ぎ澄ませて生きることを意識してはどうでしょうか。人間のすごいところは、五感で世界を認識し、考えて、手を動かしながら試行錯誤できるところにあります。私たちの身体は、もっといろんなことができるんです。それなのに、いつもパソコンの画面をにらみながらキーボードを叩いているのは、もったいないと思いますね。
張:なるほど。「五感を研ぎ澄ませる」がキーワードですね。今後、和時計に続く新しいテクノロジーや、つくりたいもののイメージなどはありますか。
菊野:いくつかやりたいことのうちの一つとして、江戸時代の和時計を昔のやり方の通りにつくってみたいと考えています。昔は実際にどのようにつくられていたか、どんな機材を使っていたか、謎なんです。それも想像しながら、江戸時代と同じような感覚でつくりつつ、どこまでできるか挑戦してみたいですね。
張:田中久重さんと同じやり方で。
菊野:今、手元にあるものは、現代のアドバンテージを受けてつくったものですからね。昔の人の追体験をして、また違う切り口でものを見られるようになりたい。そんなことを考えていますね。
張:菊野さんご自身が、時計づくりを通して、過去から時を受け継いでいらっしゃいますよね。最後に、独立時計師としてもっとも重要なことはなんでしょうか。
菊野:一人で何でもできないといけないからこそ、何か一つのプロフェッショナルになっちゃダメだと思います。時計をつくり続けていくためには、幅広い分野に興味を持って、それらをつなげる発想力を持ち、多面的に掘り下げて、自分のスタイルを確立することが重要です。自分の売りは何か、それを知ってもらうためにどうするか、固定観念にとらわれず、自由な発想で挑戦していきたいと考えています。スペシャリストとジェネラリストのどちらかに偏るのではなく、その両方を行き来するような感じですね。
張:なるほど。今日は貴重なお話をありがとうございました。

※この記事は【時間デザイン研究所】に掲載されていた記事を転載しています。内容は掲載当時のものです。

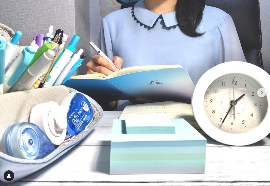


長脛彦 さん
機械式腕時計に不定時法を実装するのはまさに名人芸ですが、デジタルで再現するのは出来そうです。実際にそれに合わせて生活することで身体や心がどう反応するのか試してみたいです。