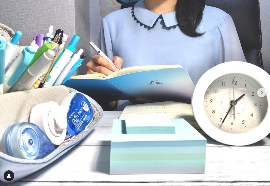時間〈とき〉ラボ運営事務局 さん

2年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックに向けて期待感が高まる中、個々のアスリートの動向にも注目が集まっている。今回は、昨年7月に開催された世界パラ陸上選手権女子走り幅跳びで見事銅メダルに輝き、東京に向けて日々練習に励むパラアスリートの中西麻耶さんに話を聞いた。
中西麻耶(なかにし・まや)
大分県由布市出身。明豊高等学校卒。テニスで国体をめざしていた2006年、勤務先での事故で右膝から下を失う大けがを負う。しかしその後、障がい者陸上に転向し100m走、200m走で日本記録を塗り替え、事故からわずか2年で北京パラリンピックに出場、100m走で6位入賞、200m走で4位入賞を果たす。以降、2012年ロンドンパラリンピック、2016年リオデジャネイロパラリンピックに出場(走り幅跳び4位入賞)。走り幅跳びのアジア記録・日本記録保持者である(5m51)。
聞き手:日本能率協会マネジメントセンター 専務取締役 張士洛
テニスから陸上競技へ

張:陸上競技の技術面やメンタル面についてお聞きしていきたいのですが、まずは走り幅跳びの面白さや難しさを教えてもらえますか。
中西:走り幅跳びは、決勝まで行くと6本の試技があります。その6本の構成を考えるとき、前半に記録を狙うのか、それとも前半は様子を見て後半に勝負をかけるのか。それによって他の選手に与えるプレッシャーも変わりますから、そういう駆け引きの部分も重要で、また面白いところでもあります。
私は事故で足を切断するまではずっとテニスの選手でした。テニスの場合は去年の大会で優勝した選手と、今年の大会で優勝した選手のどちらが強いのかという比較はなかなか難しいのですが、陸上競技の場合は一度最高の記録を出したら、それが破られるまではその人が一番です。テニスから陸上に転向して、そういうところが新鮮でしたね。
張:記録が残るということは、自分が競技を終えた後も時代を超えてトップでいられるということですね。障がい者スポーツという点ではいかがでしょうか。
中西:男子の走り幅跳びに関しては、健常者の大会と同等の記録も出ていますけれども、女子に関してはまだまだです。技術が進歩して義足もどんどん良くなっていますが、技術や環境が向上すれば記録が出るというものでもなく、いろんな要素がすべてうまくはまった瞬間に記録が出るというか。そういうところも魅力ですね。
張:本番で結果を出せる選手と、ポテンシャルは持っていても結果を出せない選手っていますよね。中西さんもなかなか結果が出ない時期もあったと思いますが、その頃と今の違いはどんなところにあると思いますか。
中西:私の場合、「本番で特別なことをしない」ということに尽きます。そのときだけのための「特別感」をなるべく出さないことですね。
張:なるほど。でも、本番で練習通りにやるのが精神的にも肉体的にもいちばん難しいですよね。
中西:たとえば、コーチが変に特別感を出すようなことを言うと良くないですね。競技をするのは私一人ですが、実際にはいろいろなサポートをしてくれる人たちとチームで闘っているので、その中の誰か一人でも意識すると何かがずれてきてしまう。でも、いまのチームはそういうこともなく、競技の直前まではいつもと同じように笑い話をしています。そして、ピットに立った瞬間、みんなが一気に集中する。そういう環境がつくれていると思います。
恩師との出会い

張:中学時代に別の学校でコーチをされていた成迫壱コーチと改めて巡り合ったというのも不思議なご縁ですよね。
中西:本当にそうです。何があるかわからないというか。
張:もともとよく知っていた方だということですが、長い時間を経て再会されたということについて、感じることはありましたか。
中西:私が通っていた中学校は、テニスがまったく盛んではありませんでした。自分はもっと強くなりたいのに、練習を見てくれるコーチもいない。でも県大会に行くと、他の学校では熱い指導者がいて、それに応えている選手たちがいる。そんな姿を見て、羨ましく思っていました。
1年生のときに団体戦で対戦した学校があって、そのときは自分たちと同じくらいのレベルだったのですが、1年ごとにどんどん強くなっていって、3年生のときには団体戦の決勝まで勝ち進んでいたんです。3年間でものすごく力をつけたのですが、その学校を指導していたのが成迫壱先生だったのです。
私は社会人になって障がいを負ってから陸上に転向したので、陸上の世界には知り合いも頼る人もいませんでした。そんなときに、たまたま講演にうかがった学校で、教頭先生をされていた成迫壱先生にお会いしたのです。
そこで自分が陸上をやっていることをお話したところ、先生はもともと陸上の指導者だったということを知ったんです。そのとき私はアメリカ人のコーチをつけていたので、すぐに「教えてください」という話にはならなかったのですが、その後海外から帰ってきて、日本でコーチを探しているときに、なんとなく先生のことを思い出したのです。
張:まさに時を超えたつながりですね。その再会がなかったら、いまの中西さんはないかもしれない。
中西:不思議ですよね。先生は私が高校の時にテニスでペアを組んでいた子の恩師でもあるんです。競技が変わっても、指導者や恩師が一緒というのは面白い巡り合わせだと思います。そう考えると、テニスをしていたことは陸上をするうえでも無駄ではなかったんだなって。
ゾーンに落ちる感覚とは

張:さて、走り幅跳びのお話しをもう少伺いたいのですが、試合のとき、助走、踏み切り、跳躍という流れのなかで、どんなことを考えているのでしょうか。
中西:「考えないこと」ですね(笑)。さっきもお話しましたが、特別なことはしない。練習のときは常に意識しながらやるのですが、それを徐々に無意識な状態でもできるように移行していく。反復しながら体にしみこませていくプロセスを経て、本番にのぞむのです。何も考えなくてもやれるだけの自信を練習で身につけていくことが大切です。
張:アスリートの方はよく「ゾーンに入る」ということを言いますが、それはどういう感覚なのでしょうか。
中西:「無」の状態でしょうか。注意が一点に集中していて、自分が求めているもの以外は何も見えない。
張:歓声とかも聞こえなくなる?
中西:聞こえなくなりますね。そして、すべてがスローモーションに見えるというか、自分の動作や時の流れがすごくゆっくりに感じられるようになります。たとえばゲームなんかでも、スローモーションだったら操作するのが簡単になるじゃないですか。そのゆっくりとした時の流れの中で、理想の動作を確実に決めていくんです。着地したときに飛び散る砂粒までスローモーションで見えたときは「来た!」って感じですね。
張:ゾーンには毎回入れるものなのでしょうか。それとも集中力が極限に高まったときだけ?
中西:幅跳びの試技6本すべてで、ずっとゾーンにいられるほどの集中力を保とうとするとさすがに疲れてしまうので、必要なときにしっかりと落ちれるように訓練しています。カウンセリングのコーチをつけて、自分でそういう状況をつくりだせるよう心理的なトレーニングに取り組んでいます。
アスリートとしての到達点

張:いままでで「これは完璧だ!」と思った試技はありますか。
中西:まだないですね。自分の求めるものが上がってきているということもあるんでしょうけれども。
張:昨年の世界選手権で銅メダルを決めたジャンプでも完璧ではない?
中西:ではないです。もちろん、ちゃんと集中できているし、自信のある跳躍ができたからこそ良い記録が出たのですが、自分のなかではまだまだやれることがあるという思いでしたね。
張:「すべてがはまった」とまではいかないということですか。
中西:「はまった」という感覚のときもあるんですけれども、そのはまる幅をもう少し広げたいという欲が出てしまうんですよね。これは性格だと思うのですが、私はスポーツをしていくうえで、「金メダルをとる」とか、「世界記録を出す」ということより、努力によってどこまで人間としての可能性や限界を引き上げることができるかに興味があるんです。だから、他の選手とは少し感覚が違うのかなという気はしますね。最近は年齢のこともよく言われるのですが、競技の面でそれを感じたことはありません。
張:限界を作らず、あくなき向上心を絶えず持ち続け、本当に強いですね。でも、誰しもが弱い面もあるはずです。自分の弱さを自覚することはありますか。
中西:練習は本当にきついので、毎日やめたいと思っています(笑)。
張:人間らしくていいですね。我々ビジネスパーソンも、時々、仕事をやめたいなと思いながら、それでも頑張って会社に来ているわけですから(笑)。そういう意味では我々と同じということですね。
中西:この日を乗り越えればオフだとか、大会が近づくと、「あと何日でビールが飲めるぞ」ってカウントダウンしています(笑)。
濃密な時間とは

張:我々は、時間には「濃い」「薄い」があると考えていますが、そういうふうに感じられることはありますか。
中西:一日が24時間であるというのは誰でも同じですが、その24時間をどう過ごすか。その積み重ねで、それこそ人生の濃さって変わってくると思うんです。私は人に「何でそんなに忙しいの」って言われるくらい、練習もそれ以外のことも凝縮した一日を過ごそうと思っていますが、それが積み重なって、いまになっているのかなって思います。
張:時間は無駄にしたくないタイプですね。
中西:そうですね。以前、競技のためにアルバイトをしていたときも、ただ働くだけでなく、いろいろと考えていました。持ち帰り専用のお寿司屋さんで働いていたとき、「昨日は30分でお弁当を15個つくれたから、今日は20個つくれるようにしよう」とか、どうすればもっと効率よくできるかを常に考えていました。定時は5時までと決まっているので、それより早く帰れることはないのですが、決められた仕事が終われば30分でも空き時間ができる。すると、その30分で腹筋ができるわけです。
張:仕事に取り組む姿勢も素晴らしい。ぜひ、うちの会社に来ていただきたいです(笑)。
世界の舞台に立って感じたこと

張:さて、4年に一度のパラリンピックの話を伺いますが、2008年の北京大会で、パラアスリートとしては上々の滑り出しとなったわけですが、世界という舞台をどんなふうに感じられましたか。
中西:実は北京のときは、日本代表としてに競技場に立つまでは「つまらない」という思いのほうが強かったんです。テニスをしていたときは、ものすごく努力をしたのに日本一になんて全然なれなかった。それが、障がい者陸上では走り始めて半年で代表入り。日本の国旗の入ったユニフォームをこんなにあっさりと手にすることができて、逆に寂しく感じたんです。
テニスをしていたときは、何年も何年も、ものすごく必死で頑張っていました。事故の後に病院で足を切断すると決めた理由も、何とかテニスを続けたいという気持ちが大きかった。そこまでしてでも、あの国旗の入ったユニフォームを着たいと思っていたのに、それがこんなにあっさり手に入るなんて…。私がテニスから転向した2008年当時、障がい者陸上は正直言って、国内では競技スポーツではなかったと思います。
でも、北京の舞台に立って他の国の選手を見たときに、やはりこれは紛れもなく競技スポーツだと確信しました。そのとき、100%の努力をしてこなかった自分を本当に恥ずかしく思いました。もっと努力できた、もっと準備できたと心から後悔したんです。
張:そこで心に火が付いた?
中西:そうですね。パラリンピックの選手村でも、日本ではなく海外を拠点として練習するには、どこの国に行けばいいだろうというのをずっと考えていました。
張:それで北京の後、アメリカに拠点を移されたわけですね。
中西:海外の選手はやはりオーラが違います。威圧感があるというか、絶対的な自信を持ってこの場所に立っているというのがわかる。それを身につけるためにどんな練習をすればいいのか、コーチはどんな指導しているのか。そういったことが、どうしても知りたかったので、思い切ってアメリカに行ったんです。
張:実際行ってみてどうでしたか。
中西:日本では、競技場に行ってまず教えられたのは義足のはき方、使い方でした。もちろんそれも大事なんですけど、それは練習時間とは別にすることであって、競技場ですることではないと思ったんです。私はずっとアスリートという意識でやってきたので、そういうもどかしさがあった。
でも、アメリカでは、義足が使えるというのは大前提で、競技場に入ったらすぐに陸上の練習が始まります。そこで、障がいがあろうがなかろうが、自分はスポーツができているんだっていう実感が得られたんです。
2020年へ向けて

張:2年後にはいよいよ東京大会です。それに向けての思いはいかがですか。
中西:自国開催の大会ですから、「中西選手を生で見たい」と思ってもらえるように、まずは魅力ある選手になりたいと思います。
張:そのためにはどんなことが必要でしょうか。
中西:陸上の大会って、どうやって応援すればいいのかわからない人も多いと思うので、幅跳びの場合だったら、手拍子を求めるパフォーマンスを積極的にしています。そうすれば観客の皆さんも「こうやって応援すればいいんだ」ってわかるし、テレビでしか見たことのない人にも「会場に行って手拍子してみたい」と思ってもらえるかもしれない。
プロのアスリートとして大事なのは、「自分が」ではなくて、「見ている人が」何を求めているのか、何をしてもらえたら嬉しいのかを考えることだと思います。なので、こちらの立場ではなく、相手の立場に立ってものごとを考えるように心がけています。
張:素晴らしいですね。アスリートは基本的に、見ている人のことまで考えられない人が多いのかなと思っていました。
中西:パラアスリートは特にそうだと思います。東京大会の招致活動では、最初は「東京オリンピック」招致活動でした。それが次第に「パラリンピック」という文言もつけなければ、ということになって「東京オリンピック・パラリンピック招致委員会」というふうになった。メディアも、これまでパラリンピックはあまり取り上げていなかったけど、なんとなく「取り上げないといけない」状況になっているというのが本音ではないでしょうか。
でもパラリンピックに、競技としての魅力が本当にあるだろうか?私はそこをもっと考えなくてはいけないと思っています。2020年までは取り上げてもらえるかもしれないけど、その先はどうなるかわからないじゃないですか。そこで終わってしまうのではなく、もっと先を見据え、自国開催というメリットをしっかり利用して、日本という国に障がい者陸上も含めた「スポーツ文化」を根づかせていかなくてはいけないと思っています。
張:先日、平昌大会の閉会式に出席されたそうですが、改めて何か感じることはありましたか。
中西:実は閉会式にはこれまであまり出たことがなくて、初めて最初から最後まで見たんですけど、作り手の思いや、その国ならではのおもてなしの心が感じられて、とても有意義でした。そのとき思ったのは、「東京ではどんな閉会式になるんだろう」ってことです。これまではもてなされる側だったわけですが、今度は自分がもてなす側になるので、そこで何ができるんだろうと、改めて考える機会になりました。
張:運営側だけでなく選手も一緒になっておもてなしをしたいという思いが芽生えたということですね。2年後がますます楽しみになりました。まずは日本代表になっていただいて、東京での素晴らしい結果を期待しています。ありがとうございました。

※この記事は【時間デザイン研究所】に掲載されていた記事を転載しています。内容は掲載当時のものです。