時間〈とき〉ラボ運営事務局 さん

時間とは何か? 誰にとっても説明が難しいこのテーマに対して、心理的なアプローチから研究を行い、一般に向けてさまざまな発信をしているのが、千葉大学人文科学研究院の一川誠教授。心理学の立場から見た時間の有効な使い方や、人生を豊かにする時間の活かし方とは。
一川誠(いちかわ・まこと)
千葉大学大学院人文科学研究院教授。
専門は実験心理学。実験的手法により人間が体験する時間や空間の特性、知覚、認知、感性における規則性の研究に従事。現在は特に、視覚や聴覚に対して与えられた時空間情報の知覚認知処理の特性の検討を行なっている。
著書に『大人の時間はなぜ短いのか』(集英社新書)、『時計の時間、心の時間-退屈な時間はナゼ長くなるのか?』(教育評論社)など多数。
聞き手:日本能率協会マネジメントセンター 専務取締役 張士洛
仕事と時間

張:今日は、先生のご専門の心理学の視点から、時間の活かし方や向き合い方についてお話しを伺っていきたいと思います。まず、わかりやすいところで、よく朝型の人、夜型の人と言いますが、時間を有効に活用するという視点からは、どちらの方がいいのでしょうか。
一川:人間の体には、サーカディアンリズム(※1)といわれる24時間周期の活動性があります。人間という生物種は本来昼型ですから、そのサーカディアンリズムから外れて起きたり、寝たり、活動をしたりしていると、体にも心にも負担がかかります。心理学的には、体と心のリズムが活動モードの時間帯に仕事をするというのが、効率性としては望ましいと考えられています。
※1 サーカディアンリズム(circadian rhythm)
概日リズム。約24時間周期で変動する生理現象で、人間をはじめとする動物、植物などほとんどの生物に存在している。
張:効率のお話が出ましたが、朝型・夜型にかかわらず、現代のビジネスパーソンの時間の過ごし方というのは、科学的にみていかがですか。
一川:意識せずに仕事をしていると、どうしても締め切りに合わせてしまうところがありますよね。それが非効率な働き方につながっていると思います。「何時まで残業できる」と言われると、その時間いっぱいまで使って残業してしまう傾向がある。日本の生産性は海外と比較して低いと言われますが、そのへんの時間の使い方にも問題があるのではないでしょうか。
張:ムダの多い働き方ということですね。一方で、締め切りが迫ってくるといつも以上の力が出るということもあると思うのですが。
一川:たしかにそういう側面もありますが、締め切りギリギリにならないと仕事を始めない人というのは、心理学的には、自分を不利な状況まで追い込んで、できなかった場合の言い訳の余地を残すという自我防衛機制(※2)が作用していると考えられます。やはり早めに、少しずつこなしていくほうが、効率的で質の高い仕事ができると思います。ゴールに近づくほど、その仕事に対して積極性が高くなりますし、やっていて楽しくなりますよね。締め切りギリギリになって慌ててやるよりも、早めに着手することが大事だと思います。
※2 自己防衛機制
自分自身の感情的価値の低下や、自尊感情が傷付くことを避けるため、不安・苦痛・罪悪感・恥などの感情を引き起こす事実認識を無意識的に抑制し、精神的な安定を図る心の働きのこと。
張:我々もマネジメントの分野では、PDCAを推奨しているのですが、きちんとした計画を立案するとともに、途中で小さなマイルストーンをつくって、それをひとつずつ乗り越えることが理想的だと考えています。
一川:そうですね。小さな目標であれば達成しやすいし積極的になれるので、そういう段階を設けて大きな作業を進めていくという仕事の仕方は、人間の心理的特性に合っていると思います。
働き方改革と時間の使い方

張:いま、多くの企業では働き方改革がキーワードになっていますが、効率という点から見て、働き方改革を成功させるためのポイントは何でしょうか。
一川:日本の企業では、時間あたりの成果についてはあまり追求されていない気がします。たとえば、「やらないよりはやったほうがいい」くらいの仕事がすごく多いと思いませんか。それと、専門外の業務に時間を割かれていることも多いと感じます。経営的な視点からすると、これらは効率的とはいえませんね。
張:自分の専門とは違う仕事をすることで非効率になっていると。
一川:私はカナダで研究員をしていたことがあるのですが、そのときの時間の使い方と比べると、大きな違いを感じます。海外では基本的に、専門を持っている人は、その仕事しかしません。もちろん、それ以外の仕事も多少はありますが、その量は日本とは比べものになりません。
張:大学の先生も、研究とは直接は関係のない事務の仕事が多いとよく聞きますね。
一川:海外から優秀な研究者を連れてきても、日本の環境だと良い仕事ができないとよく言われますね。それで優秀な人材が日本に残らないとしたら、大きな問題ですね。
優先順位のつけ方

張:効率ということでいうと優先順位のつけ方もポイントになると思うのですが、難しい仕事と簡単な仕事では、どちらを先にやった方がいいのでしょうか。
一川:「難しい」「簡単」というよりも、自分にとって「重要」かどうかで考えたほうがいいでしょうね。重要だとわかっていれば、難しくてもモチベーションを持って取り組めますが、さほど重要でなく、ただ単に難しいだけという仕事は、始めることさえおっくうですから。
張:仕事を抱え込みすぎないことも大切ですが、日本人にはそれができない人も多いですよね。
一川:日本の職場では、自分が会社に最も貢献できる専門性を本当は持っているのに、それが生かせない環境で仕事をしていることが多いですね。ゼネラルに、いろんな仕事ができるというメリットもあるとは思いますが、海外ではもっと自分の専門性をシビアに見ています。だから、専門外の仕事については「他の人に任せたら」ということになりやすいのです。
年周期でも体内リズムは
存在する?

張:ご著書の『「時間の使い方」を科学する』に、記憶は夕方、論理的思考は午前中がいいと書かれていますね。それは一日のなかでのことだと思いますが、季節ごとにもあったりするものなのでしょうか。
一川:あると思いますね。サーカディアンリズムとは異なりますが、年周期の体内時計はあると言われています。ただし、細かいところはまだわかっていないようです。大まかにわかっていることとしては、日本のように四季のある環境下だと、暑い時期は代謝が高くて、寒くなると落ちます。秋口や春先は、また違う代謝の状態のようです。一般的には、代謝が高い時期のほうが記憶課題の成績は良いと言われています。それに応じて、たとえば、この時期は記憶に使うとか、創作的なことに使うといったような配分をするといいかもしれません。
張:ということは、予備校の夏合宿などは、一番いい時期に記憶しているということでしょうか。
一川:そうかもしれませんが、年を通しての代謝の変動よりも、一日のなかの代謝の変動のほうが大きいので、受験勉強に関しては季節というのは、あまり関係ないと思います。
張:やはり、毎日の積み重ねが大切ということですね。徹夜して勉強するよりも、夕方とか代謝のいい時間帯に集中してやるほうが効率的だと。
一川:そうですね。特に短期記憶と呼ばれるものは、夕方の時間帯のほうが圧倒的に良いのです。夜になって入眠すると、夕方あたりに覚えた記憶表象の体系化が行われます。専門用語で記憶の精緻化というのですが、記憶表象のリンクというか、連携性ができていくのです。つまり、睡眠後に記憶が定着するということですから、受験勉強で「睡眠時間を削ってまで…」というのは、実はよくありません。もちろん、寝すぎも考えものですが(笑)。
モチベーションを高く保つためには
張:時間を有効に使うことと、精神的なことはどう関係してくるのでしょうか。たとえば、失敗をいつまでも引きずってしまって、仕事が手につかなくなる、なんてこともあります。あるいは、失恋や家族の不幸など。そういったことから早く立ち直るための、気分転換のコツはありますか。
一川:人間は誰でも、成功すると嬉しくなるものです。だから、成果がわかりやすい課題に取り組んで自分を評価するとか、他人に評価してもらうといったシチュエーションがあるといいと思います。落ち込んでいても、人から評価されるようなことがあると、積極的になれます。
張:課題とは、具体的にはどんなことでしょうか。
一川:大きな目標でなくても、コツコツと積み上げていくものでいいのです。たとえば、会社であれば何かの企画を提案し続けていれば、それが採用されたり評価されたりすることが必ずあるでしょう。そういうふうに、評価がわかりやすく出ることに取り組むことが有効だと思います
不定時法の時代は
どうだったか

張:少し話が変わりますが、江戸時代以前の日本は、一日が24時間と決まっている「定時法」ではなく、一時(いっとき)の長さが季節によって異なる「不定時法」でした。先ほどの四季の話と関連してくるかもしれませんが、不定時法のメリットやデメリットは何でしょうか。
一川:まずメリットとしては、自分のペースで仕事や生活がしやすいということでしょうね。明るくなったら仕事を始めて、暗くなったら仕事を終わりにするということなので、オン・オフがはっきりしやすい。それに対してデメリットは、冬の一時と夏の一時では長さが違うわけですから、冬と夏で同じような仕事の仕方はできないということです。先ほども言いましたが、冬のほうが体の代謝が低いので、夏の間は一時間でできた仕事が、冬になるとできないということもあり得ます。そういう、一時あればどのくらいの仕事ができるのかという見通しを立てるのが難しかったのではないでしょうか。
張:太陰暦ですから、一時だけでなく、一年の長さも違っていたんですよね。
一川:閏月を設けたり、ひと月多い年があったりとか。給料計算などは難しかったでしょうね(笑)。まあ特に職人は出来高払いですから、月給という概念はなかったと思いますが。
仕事に追われないようにする
張:一川先生ご自身が、時間をうまく活用するために実践していることなどはありますか。
一川:やはり、大事なことは早めにやるようになりましたね。あとは、自分の時間の使い方を考えて、「これを受けるとパンクする」と思ったら、他の人に任せるようになりました。昔は全部引き受けるタイプだったので、仕事に追われて大変でしたが(笑)。
張:人に仕事をお願いできるネットワークを普段からつくっておくことも大切ですね。でも、人に頼むのが苦手な人というのも多いですよね。
一川:会社のなかで、頼みやすい仕組みをつくっておくといいかもしれませんね。ただ、そういう仕組みをボトムアップでつくるというのは難しいと思うので、トップダウンで進めたほうがいいものができると思いますが。
張:マネジメントについて、「自分の考えを、人を動かして実現すること」と定義していたのですが、だんだんそれが言えなくなってきました。プレーイングマネジャーが多くなってきて、人を動かすけれども自分も動かなくてはならないようになってきたのです。以前は係長や課長に部下がいて、降りてきた仕事を部下にやらせるという図式が成り立っていましたが、これが崩れてしまったのかなと感じることがあります。
一川:さっきの話ではないですけれども、目前の仕事にかかりっきりになってしまうと、やはり大局的な視点からものが見えづらくなりますね。ちょっと「引いて」見られる立場の人がいるということが組織にとってはすごく大事だと思います。
張:実務にあたる時間だけでなく、「考える時間」もないと、次に進めないですよね。
一川:空間と同じように、時間も近づいてくると目の前のことしか見えなくなります。ある程度「間」をとって、離れたところからでないと全体を見渡すことはできないから、大局的な判断が難しくなってしまうんです。
満足度の高い時間を
過ごすためには

張:いまの「見通し」の話ともつながると思うのですが、過去の経験から学ぶときに、手帳を使って記録をとったほうが、振り返りとか見通しを立てるときに有効だと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
一川:その通りだと思います。人間というのは、うまくいかなかったことの記憶はあまり残らないんですね。これは先ほど出てきた自我防衛機制に関連するもので、ここが足りなかったとか、ここがうまくいかなかったといった自分に不利なことはあまり認識をしないし、記憶もしないという特徴があります。自尊感情というか、自分の価値を下げないという心の働きかけが起こるのです。でも、手帳という日時を含めた記録として物理的に残しておけば、あとから振り返ることが可能になりますね。
張:手帳も、予定を書いただけで終わってしまう人がほとんどで、予定に対してその結果がどうだったかを検証する人は少ないですね。
一川:後日の検証はとても重要ですね。時間の見積に対して、結果的にどのくらいかかったかという両方を書き留めておく習慣をつけるといいと思いますよ。
主体的な 満足度を
上げて いくためには

張:時間をうまく生かすという意味で、ここまで生産性や効率化をテーマにお話しいただきましたが、もう一つ、どうすれば個々人が主体的な満足度を上げていけるのかというテーマがあると思います。とくに時間デザインではこれが重要だと思っていますが、その辺はいかがでしょうか。
一川:忙しすぎて、自分が何を成し遂げたのか、あるいは成し遂げられなかったのかということさえわからないくらい、ずっと走り続けているような状態だと、満足度は得られないし、時間の使い方としてももったいない。つまり、常に仕事に追われている状態というのは望ましくないということですね。その時々で振り返ったり反省したりすることが必要です。
張:忙しくても、しっかりと振り返る時間をとると。
一川:そのくらいの余裕が必要です。振り返りをすることによって、この仕事は努力してここまでできたとか、あるいは努力したけれどもできなかったという記憶が残るのです。すごく忙しかったとか、退屈だったとか、そういうことはマイナス感情として一括りになってしまうので、心理的な満足度にはつながりにくいのです。
張:満足度とか充実感でいうと、休日の過ごし方というのもポイントとしてあると思います。休日の過ごし方や時間の使い方のコツはありますか。
一川:休日だからこそできることもあると思います。忙しいと疲れていてダラダラと寝て過ごしてしまうこともありますが、そういう時間の使い方をしてしまうと、休日ならではの特別な記憶が残ることにはなりません。特別なイベントを設けて、記憶に残せるようなことがあると、個人の満足度はより高くなると思います。たとえば旅行に行ってみるとか、演劇や映画を観に行くとか、そういうふうに使ったほうがいいでしょうね。
張:一つひとつのイベントをかけがえのないものにすることが大切ということですね。なるべくルーティンにしないことがいいのでしょうか。
一川:たとえばお正月や地域のお祭りのように、毎年この時期になるとやるよね、みたいなルーティンはむしろ重要ですが、寝だめみたいなルーティンは時間の使い方としてはもったいないですね。であれば、寝だめしなくても済むような毎日の過ごし方を考えたほうがいいと思います。
張:昔ながらの行事やイベントには意味があったということですね。
一川:昔は割とどこでもあったと思うのですけれども、共同体から離れて都市生活をするようになると、こっちから出かけていかないとそういう体験ができない。つまり、ちょっと努力が必要になってしまっているなということですね。これは日本だけでなく、世界的にみてもそういう傾向が見られるようですが。
張:それは特別な記憶を一つひとつ残していくという意味ではマイナスですね。
一川:そうですね。地域のお祭りなんかは、みんなと特別な時間を共有するいいシステムだったと思うのですが、それがどんどんなくなっていくというのは、記憶を豊かにし、満足感を高めるという点ではマイナスの方向だと思います。
張:いまのお話とも関連すると思いますが、楽しいと感じる時間を長続きさせるコツというのはありますか。
一川:細かいディテールに配慮すると、長く、より豊かに体験できるようになります。たとえばスポーツをするにしても、新しい道具にしてみるとか、フォームを少し変えてみるとか。そういう工夫をして、いろんなことに注意を向けると、時間を長く感じられるようになります。
時間デザインに ついて

張:さっきの不定時法の話ですが、「時間デザイン」をなぜ「ときデザイン」と読ませるかというと、いまの時代、東洋思想が大事だと思っているからです。時間(じかん)と読ませてしまうと、24時間の定時法になってしまうので、あえて「とき」と呼ぶことで、先生のおっしゃっているような時間の伸び縮みとか、濃い薄いといったことを問うていきたいのです。つまり社会は定時法なのですが、自分のなかでは不定時法の要素を取り入れて、豊かな時間を意識して過ごすこと。それが「時間デザイン」だと思っています。そういう意味では、「My不定時法」みたいな提言できると面白いなと思っています。
一川:面白い考え方だと思いますね。同じ一時間でも、人によって感じる長さとか濃さは異なりますよね。それぞれの人がどう時間を使うと満足できるのか。時間の使い方って、人の生き方でもあるので、人から「こうしなさい」と言われるものではない。自分で積極的に考えてオーガナイズしてもらったほうが満足度も高まるでしょう。
張:時間はまさに「命」ですね。いまみたいな世の中だからこそ、「タイムマネジメント」から「タイムデザイン」へ、そして「タイムイズマネー」から「タイムイズライフ」へというパラダイムシフトを提言していきたいと思います。
本日はありがとうございました。
※この記事は【時間デザイン研究所】に掲載されていた記事を転載しています。内容は掲載当時のものです。

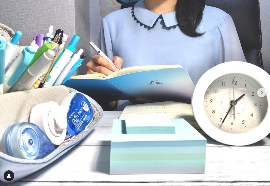

長脛彦 さん
1日の不定時法だけでなく、1つのプロジェクトでも早期着手の効用、人生全体を見ても今この時の重要性など、時間は一様ではない。これを視覚化する手帳があると良い。