時間〈とき〉ラボ運営事務局 さん

ボーイズラブの分野から一般文芸にも進出し、2020年、『流浪の月』で第17回本屋大賞を受賞。世間とうまく折り合いをつけられない登場人物の心の機微を精緻な筆致で表現し、多くのファンの心をつかんだ作家の凪良ゆう氏に、作品を生み出すイマジネーションの源泉や、時間デザインについて聞いた。
凪良ゆう(なぎら ゆう)
滋賀県生まれ。2007年、『花嫁はマリッジブルー』で本格的にデビュー。以降、各社でBL作品を精力的に刊行し、デビュー10周年を迎えた非BL作品『神さまのビオトープ』を発表、作風を広げた。巧みな人物造形や展開の妙、そして心の動きを描く丁寧な筆致が印象的な実力派である。主な著作に『未完成』『真夜中クロニクル』『365+1』『美しい彼』『ここで待ってる』『愛しのニコール』『薔薇色じゃない』等。2020年、『流浪の月』(東京創元社)で第17回本屋大賞を受賞。近著に『わたしの美しい庭』(ポプラ社)、『滅びの前のシャングリラ』(中央公論新社)。
聞き手:日本能率協会マネジメントセンター 代表取締役 張士洛
カスタマーリレーション部 JHC推進室 長岡萌以
作品のイメージは、最初はフワッと
風景が浮かんでくるように。

――第17回本屋大賞を受賞された『流浪の月』のストーリーや登場人物は、どう思いつかれたのですか。
凪良:よく質問されるのですが、なかなか説明しづらいのです。小説を書くときに、きっかけとなるアイデアは結構たくさんあって、あるときフワッとやってくるのですが、自分の中でひとつの物語として芽が出るというか、育っていく感じになって、作品として成立するのは1つか2つなんです。
――はじめに登場人物ありきではないのですね。
凪良:アイデアが膨らんでいくのと同時に登場人物も、朝顔の芽みたいに飛び出してくるというか、そんな感じでした。『流浪の月』は、人物よりもお話の全体的な雰囲気が風景みたいに浮かんでいて、そのなかにちょっとずつ、何か人影のようなものが現れてくるというか。でも、いつもそういうわけではなくて、先に会話が浮かぶ時もあれば、ストーリーが浮かんでくるときもある。きっかけは、いろいろなパターンがあるのです。
――どの登場人物も、とてもリアリティーをもって描かれていますが、なにか意識していることはあるのですか。
凪良:私はいつも、登場人物になりきって書きます。『流浪の月』で更紗を書いているときだったら、更紗になって書くし、文を書いているときならば、文になって書いています。感情移入するとか共感するとかではなくて、「自分が更紗になる」感覚です。
――登場人物だけでなく、花瓶に生けたお花や鉢植えのトネリコ、オールドバカラのグラスなど、小道具も印象的です。これらは、こだわって作品のなかに置いているのですか。
凪良:私は、ものに囲まれすぎると息苦しく感じてしまうので、どちらかというとガランとしたところが好きなんです。だから、家にはあまりものを持たないようにしています。ただ、小説を書くときは、登場人物が好きそうなものとか惹かれそうなものを、彼らの視点で選んで集めてみることはあります。小説に出てくるからといって、ふだんから集めているとか、愛でているとか、そういうことはありません。
音楽から得られるインスピレーション。
登場人物ごとにプレイリストを作成

――音楽からインスピレーションを得ることはありますか。
凪良:実は、音楽がないと書けないタイプなんです。フワッとしたアイデアがやってきたときに、まず、そのフワッとしたアイデアに合うような音楽を選んで聴く。聴いてもイメージが広がる曲と、全然広がらない曲があるのですが、広がる音楽が見つかったら、それをどんどんプレイリストに加えていく。そして、人物ごとにプレイリストをつくるんです。更紗だったら更紗の、文だったら文の、というように。
そうやってプレイリストをつくって聴きながら書き進めていくと、人物が動き出す。すると、最初につくったプレイリストのほうが登場人物のイメージと合わなくなっていくんですよ。そうしたら、その曲はプレイリストから外して、その登場人物に合う曲をまた入れる。そういうように、小説を書き進めるにつれて、プレイリストもどんどん変化していくんです。
――音楽とともに、作品が仕上がっていくと。
凪良:本当に集中すると音楽も聴こえなくなるのですが、作品を生み出す過程では、そういう感覚を重視しています。そのきっかけにさせてもらっていますね。
――ちなみに、どういったジャンルをお聴きになるのですか。
凪良:オールジャンルです。更紗を書いているときは、しっとりとした曲でしたね。ロックはちょっと合わないですから。あと、インストゥルメンタルも。『流浪の月』は、全般的に静かめの曲が多かったかな。『滅びの前のシャングリラ』だったら、ロックが中心でしたし。そうやって作品ごとに違うので、結果としてオールジャンルになってしまう。
――かなり幅広く聴かれているということですね。そうじゃないと、曲が頭に浮かんでこないのでは?
凪良:最近助かっているのは、定額制のミュージックライブラリです。外国の音楽も含めて、自分の知らない曲がとにかくたくさん入っているので、曲が浮かばないときはランダム再生をしておいて、たまたま気に入ったものがあればプレイリストに加えたりと。そういう便利なものが登場してから、幅が広がりました。
――イマジネーションはどう養われていったのでしょうか。影響された作品とか、体験がおありになるのでしょうか。
凪良:私は、小さいころから、小説にしても音楽にしても、どちらかというと現実逃避が目的で、読んだり聴いたりしてきました。趣味や楽しみとはちょっと違うのです。そういう意識が元になっているのかもしれません。自分がいま書いている物語の内容も、現実の世界に居づらい人たちのことを書いているので、やはりつながってはいるのだろうと思いますけれども。
ボーイズラブ作品でデビュー。
制約の多いなかで、作家としての基礎を身につける

――職業作家として基礎を固めていった時期には、どんなご苦労があったのでしょうか。
凪良:ボーイズラブの場合、メインテーマは恋愛で、しかも男性同士。そして、ハッピーエンドでなくてはならないという3つのルールがあります。また、ボーイズラブはエンタメの世界ですから、読者を楽しませなければなりません。こうしたことは書き出す前から決まっていることなので、そういう制約や条件のなかでいかに物語を組み立てていくか。そして自分らしさを出せるか。そういう点ではかなり苦労したし鍛えられましたね。
一般文芸を書いていると、とても自由で解放されたような気分になりましたが、一方で、それはボーイズラブの世界で10年以上も鍛えてもらったというベースがあるからこそなんだと、あらためて実感しました。最初から自由だったらそうはいかなかったかもしれません。基礎がしっかりとできていたからこそ、好きな方向に泳いでいける筋肉がついたのだと。
――会社組織でも、いろいろな制約があるなかでどうやって自分らしく働いていけるかが問われます。
凪良:私は飽きっぽい性格で、何をしても長続きしないのですが、小説を書くことだけは長く続けられています。それは、いろいろな縛りがあっても好きだからこそできたのだと思います。反面、いくら好きでも、最初から好き勝手やってしまったらダメだったと思うんです。ボーイズラブ作品を制約のあるなかで書き続けた経験というのは、いまおっしゃった組織のなかで自分らしさを出すということと通じるかもしれませんね。
――鍛えてくれたのは、当時の編集担当者ですか?
凪良:特定の誰かというよりも、業界やジャンル全体に鍛えてもらったんだと思います。私の場合、自由な表現を制限されることを割とポジティブにとらえることができましたが、あまり制限をかけすぎるのも、作家にとってはよくない。編集者によっては、塩梅を見てくれる人もいれば、限りなく制限をかけてくる人もいる。いろいろなタイプの編集者がいますが、作家が潰れない程度に制限をかけて、なおかつ読者を楽しませるような作品を書かせる。そういう編集者と出会えたら幸せですよね。
――制限があるなかで、どうやって自分らしさを出す工夫をされていたのですか。
凪良:幸いにして、小説を書くことに関してだけは粘れる人間だったので。それ以外は全然ダメなんですが(笑)。「こういう書き方はダメ」と編集者に言われても、諦めずにどういうふうに書き直せば認めてくれるのかをずっと考えて、何度もプロットを出し直したりしたものです。ですから、当時の編集者にとっては扱いにくい作家だったと思いますよ。言うことをストレートに聞かないですから。
筆が進まないときほど、気分転換はしない。

――一日中書いていられるタイプだと伺いましたが。
凪良:本屋大賞をいただいてから、ありがたいことに小説以外のエッセイやコラムを書く機会をいただくようになりました。これまで、書くことだったら一日中でもやっていけると自認していたのですが、エッセイやコラムだと全然集中力が続かないことに気づいたんです。同じ「書く」仕事なんですが、15分くらいすると、飽きっぽい私が頭をもたげてきてしまう。だから、同じ「書く」でも、きちんと続けられるのは小説だけなんだと思い知らされました。
――どんな作業環境で書かれているのでしょうか。
凪良:朝起きて書き始めるときは、立って書きます。ちゃんとしたスタンディングデスクまでは使っていないのですが、ちょうどいい高さの本棚の台があるので、そこにノートパソコンを持ってきて、書き始めるのです。お昼過ぎになるとノートパソコンのバッテリーが切れるのですが、そうすると机に戻らざるをえなくなるので、机に戻って電源を差し込んでまた書き始める。そこからは、座っての作業ですね。それは、小説を書くスタイルというよりも、ずっと座っていると寿命が短くなるとか、腰痛が悪化するとか、そういう理由です。 でも、ずっと立って書いた後に机に移動して座ると、また集中し直せるので、すごくいいことだと思います。
――ちなみに、一日に何文字くらい書けるものですか?
凪良:まちまちですね。私はパソコンの画面を単行本の見開きページに設定していますが、調子がいい時は一日10ページ(見開き)くらいでしょうか。でも、調子が悪いと2ページくらいしか書けないときもあるので、書くスピードとしては遅いほうだと思います。
――筆が進まないときは、どうしているのですか。
凪良:そういうときは散歩にいくなど、気分転換する人のほうが多いと思いますが、私は書けない自分に腹が立ってしまうタイプなので、是が非でもこの場から動いてやるものか、と思ってしまうんですね(笑)。そういうときほど意地でも動かない。原稿に向かい合う。逆にうまく書けているときは、「もしかしたら筆が滑っているかも」と怖くなってしまう。だから、うまく書けているときのほうが、散歩に行ったり食事をしたりと、気分転換するようにしています。
『流浪の月』は、主人公2人とときを旅するように読みたい

――さて、「時間デザイン」についてもお伺いしたいと思います。日本語は、「とき」という概念がとても豊富な言語です。ご自身は、創作活動をするとき、あるいは生活において「とき」をどのようにとらえているでしょうか。
凪良:私は、仕事をするときは「時間」を気にしますが、仕事から離れると「とき」になると思っています。
そういう意味からすると、一日のうちで最も「とき」を意識するとしたら、夕暮れどきのひとときですね。ほんのわずかなんですが、空気が青くなる時間帯があるんです。そういう時間帯に部屋の電気を消して薄青い空気を感じながら一息つく。横になってみる。それが、「時間」ではなく「とき」を感じる瞬間ですね。ゆったりした気持ちになるし、たとえ疲れていたり悲しい気分であったりしても落ち着く。そういう「とき」が、一日のなかでは必要ですね。
――いいですね。日本人として「とき」の大切さをもっと主張したいですよね。
凪良:「時間」というと、短いものに感じてしまうものですが、「とき」というと、もうすこし長いというかゆったりした響きがありますよね。
――作品中で「とき」を意識することはありましたか。
凪良:『流浪の月』では、更紗と文の最初の出会いから15年後にまたいろいろな出来事が起こる。エピローグのファミレスのシーンは、そこからさらに何年か後のことです。というように、とても長いスパンを描いた作品ですから、この作品自体が「とき」をテーマにしているともいえなくはないですね。
そういえば、『流浪の月』の読者向けのメッセージカードに「2人といっしょに長い旅をするように読んでほしい」と書いたことを思い出しました。この「長い旅」が「とき」なんでしょうね。
――いつも、作品のなかに読者に感じ取ってもらいたいメッセージを込めているのですか。
凪良:書きたいものは、自分できちんと持っているつもりですが、それを読み手に無理に伝えようとは思っていません。むしろ、読み手が自由に何か感じてくれるほうがいい。それが自分の考えとマッチしていれば、幸運な出会いと言えるでしょう。そういう出会いがたくさんあるといいですね。
――作中にメッセージを打ち出すというよりも、そこに共感が生まれれば嬉しいと。
凪良:そうですね。自分が読者の立場でも、「あなたを元気づけようと思って書きました」とか言われると、パーッと冷めてしまう(笑)。そうではなく自由に読みたいんだよって。だから、書き手になった時も、人それぞれ、自由に感じて、読んでもらえたらいいなと思っています。
――これからも、読み手が自由に感じて、読める作品に期待しています。本日は、ありがとうございました。

拝啓 あの日の自分
「職業作家としての決意を固めた頃の自分へ」
7、8年前にプライベートに大きな変化があって、以来、心の中にいろいろな感情が渦巻いています。大好きな小説を書きたい、自分の欲求を貫きたいからといって、大事なものを手放していいのかという葛藤。もう引き返すことはできないぞというプレッシャー。
そういう気持ちの自分に、「崖っぷちでも大好きなことを続ければいい。そうすれば本屋大賞だっていただけますよ、頑張りは必ず報われますよ」って、言ってあげたいですね。
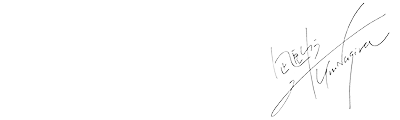
※この記事は【時間デザイン研究所】に掲載されていた記事を転載しています。内容は掲載当時のものです。





長脛彦 さん
たくさんのアイデアのうち作品として成立するのは1つか2つ。サブスクからアイデアに合うような音楽を聴いていると,アイデアが膨らんでいくのと同時に登場人物たちが芽吹いてくるので,その登場人物になりきって書く,という。「いっしょに長い旅をするように」書き,そう読んでほしい,とも。
小説を読んで,そのアイデアが透けて見えることがある。だが,それは蒔かれたままの種ではなく,新たに結実した種なのだろう。